安物ってなんだろうか?
- カテゴリ:日記
- 2010/05/30 21:38:13
安売りのタオルを買ってきまして、とりあえず洗濯しました。
他に、買ったばかりのスラックスも一緒に投入。
洗濯機が止まって中を見ると、
全てが埃まるけ。
タオルから出たケバケバである。
タオルの袋には注意書きで「毛羽立ちが出ることがあります」とあるのだが、それにしても…
まあ、安物だからしかたない。とは思う。
それよりも、不思議なことがある。
安物だから木綿の繊維が出てしまう。そのことの方が不思議だ。
繊維を寄り合わせて糸にする。
それを織り上げて、タオルにする。
人件費を安くしたり、染める色を、値段の安い染料にして、単純な色にする。それで値段が安くなるのはわかるのだが、
埃がたくさん出る。というのは値段と比例するのだろうか?
木綿の糸の製造で、何らかの手抜きをしたとして、どういう製法にすると埃が出るのだろうか。
木綿糸の製法を知らないので想像できない。
原材料の問題が大きいのかな?
でも、それだと、糸の製造工程が、逆に難しくなってしまう気がする。
世の中、コストダウンという言葉が幅を利かしているが、ある程度コストを下げると、それ以下は「ある」か「ない」か二つに一つだと思う。
中途半端な安物は、はなから成立しないはずだ。
無理なものは無理だろう。
埃を出したタオルが、そういう「物」として成立したことが不思議だ。
それにしても、お金は払うべき時に払った方が良い。
ちなみに「ほこりまるけ」は東海道の方言です。
検索して調べても、方言なので決まった漢字はありません。
ただ、無理に漢字にすれば「埃丸怪」になると、僕は思います。
「怪」は「もっけのさいわい」などの「物怪」「勿怪」です。
人によって「ほこりだらけ」と訳しますが、「だらけ」では、広い部屋の床に埃が散らばっているような状態でも「ほこりまるけ」になってしまいますが、そういう場合には「ほこりまるけ」とは言いません。
なんらかの物体に、たくさんの埃がまとわりついている様子が「ほこりまるけ」です。
「まみれている」「まとわりついている」などの「ま」です。
タンスの裏に落としたミニカーをようやく隙間から引っ張りだしたら、埃まるけだった。みたいなことです。





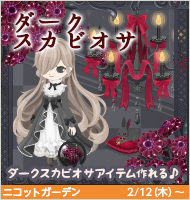














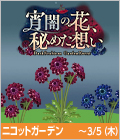






タオル独特の糸の輪があるパイル織で、輪の先端を刈り込んで輪を切るシャーリングがある。これは、糸を切るので、必然的に、糸の先端から埃が出続ける。洗うごとに布がやせてゆく。
タオル用の木綿糸と、一般の布を織る糸では、よりの強さが違う。
布ではしっかりと撚りをつけた糸なので、丈夫でほつれが少ない。それで、埃が少なく、洗濯でも糸がやせるのが遅い。
逆に、タオル用は撚りが弱めなので、柔らかい糸になる。そのかわり、洗濯などで繊維が抜けて、どんどんやせてゆく。
布は古く弱くなっても、それほどやせないが、古いタオルは、新品と比較して大きな差を感じるほどやせる。
高級タオルでは、まったく撚りをかけない糸を使う事もあって、これは、厚みがあって非常に柔らかな仕上がりになるが、寿命が短い。
で、
どうやら、タオル用の糸の撚り加減など、ちゃんと考えられたタオルでは、丈夫で長持ちするのだが、ただ撚りを弱くしただけのタオルでは、どんどん繊維が抜けてしまう。
高級品は、あえて、寿命が短くても撚りを弱くして、柔らかいタオルにする。
ということで、僕の記憶にある、一昔前の中級品が、いちばん硬くて丈夫。
だったらしい。
洗っても洗顔後、顔に付くので困ります。
スラックスはネットに入れて洗いましょう。
コストダウンのために無駄を省く、よけいな事はしない、というともっともらしいけど、できる事をできるだけやる、ということも否定している。
「やるな」ではなくて「これをやる」という姿勢でいたいのだが、そういうひとは今時の日本では暮らしにくいのだった。
せめて洗濯ネットに入れれば良かったですね。