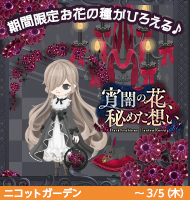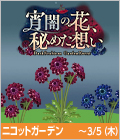蝶々夫人の修正は正しいのか
- カテゴリ:日記
- 2010/06/16 22:44:13
日本テレビの「笑ってコラえて!」で紹介されていた話題。
オペラの「蝶々夫人」には間違いがあり、日本人が修正して上演する、という。
そこで間違いの例としてあげられたのが
『蝶々がアメリカ人と結婚するためにキリスト教に改宗するとき、仏教の坊主が「神、猿田彦の罰が下る」と言うのだが、これは仏教と神道を混同している』
ということなのだが、、、。
さて、これは、
どう考えたら良いだろう、と、僕は迷ってしまった。
僕は蝶々夫人のことはほとんど知らないが、舞台は1890年ごろだという。
この、1890年に引っ掛かったのである。
まず、江戸時代の日本は仏教が基本だと、僕は思う。
宗教家の解釈や、歴史家の定義は知らないが、一つの知識として言えるのは、徳川家康は、政治的な判断で、神道と仏教の境目をあいまいにしてあつかったことがあげられる。
日本の実権を握った家康にとって、政治としての天皇と、宗教としての天皇の、両面をおさえなければならなかった。
特に、政治的にも、豊臣秀吉が公家を使って権力を強めた影響が残っている時代だ。
政治の実権を武力によって握ったのは良いが、民間の信仰として天皇が神であり、感覚的な意味での権威は、依然として残っている。
民衆の心理をつかむためには、家康にとって神道は邪魔であるが、つぶすこともできない存在だった。
それで、両者の教義を比べて、つじつまを合わせつつ、二つのものは、根底ではつながっていると説明した。
家康は死後「大権現」となったが、これは、仏教で言う「ほとけ」の一つの形の現れである。
仏は、この世に満ちていて、そのときどきで、何らかの姿で現れる。
神道で言う「神」も、仏教から見れば、仏が「神」の姿となって現れたのである。
ということになる。
家康は、自ら仏であり、神として日光にまつられた訳だ。
余談だが、この神道と仏教の融合は聖徳太子のころには始まっている。
古くから、中国や朝鮮からの思想の輸入の中で、神仏習合のようなものが起きている。
そうした日本の昔からの思想が根底にあるおかげで、家康は神である天皇家と、仏教を混ぜ合わせることに成功した。
さて、話しが走ってしまった。
蝶々夫人の話題へ戻る。
1890年は、明治維新後だ。
明治政府は、天皇家の威光を強くするために、廃仏毀釈を行った。
家康が行った神仏習合を否定して、神がもっとも上位であるとした。
1870年ころに、明治政府の法律として、神仏分離が行われている。
すると、、、、
ここが重要だ。
1890年の仏教はどんな状況であったか。この疑問が浮かぶのである。
廃寺をまぬかれ、生き延びるためには、習合している神仏の、神の方を第一と言わなければならない。
仏教の寺でありながら、「仏が現れた形の一つである神」の立場が逆転し、「神の解釈の一つがほとけである」という方便が使われることになる。
さて、ようやく話しが蝶々夫人へ戻った。
蝶々夫人の中で坊主が言った言葉、「神、猿田彦の罰が下る」は、当時の日本としては「あり得る話し」ではないだろうか。
少なくとも、日本の細かい事情を知らない外国人が、仏陀ではなく、猿田彦の名前を使ったということの方が、「よくぞ調べた」と、僕は感心するのである。
明治政府による国家神道の時代であれば、寺の坊主であっても「猿田彦」の名前を挙げて間違いないのである。
あくまで、僕の頭の中で知っていることを付き合わせてみたが、どうだろうか。
はたして、当時の日本人の、本当の姿は、どんなものだったろうか。