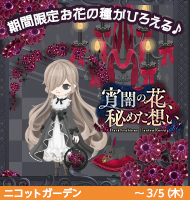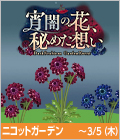創作物としての蝶々夫人
- カテゴリ:日記
- 2010/06/17 22:53:10
前回の記事は、テレビを見てすぐ頭に浮かんだものを書き留めたので、読んでわかりにくい文でした。
いちおう、要旨の整理をします。
-----
まず、自分の知識の中で、手の届かないものが「明治維新」です。
本を読んでもよくわからない。
蝶々夫人の舞台は、明治維新1868年からしばらくした時期。
1890年程度の物語です。
この頃は、時代背景として、明治政府が天皇を看板に押し立てて権力を確立したすぐ後の時期です。
本音と建前の問題があり、実際は倒幕した明治新政府が実権を持っていますが、名目としては天皇は政治権力の中心です。
この天皇を大看板として、明治政府は国の宗教を神道にし、天皇を神として日本の中心にします。
このため、国の法律として仏教は廃止され、過去の日本の思想が否定されます。
さて、ここで一つ、現代の日本人から見て、はっきりわかることと、わからないことがある。
今でも仏教は生き残っているし、思想として問題なく受け継がれている。
これは明白だ。
それでいて、明治から昭和、太平洋戦争で敗戦する前までは、国家神道だった。
仏教の寺は廃止されているはずの時代を、細々と生き残って来た。
つまり、疑問として、仏教はどのように廃寺を逃れたのかが問題になる。
現代の日本人から見て、当時の日本の事情は、わかりにくいのである。
ここでひるがえって、蝶々夫人で描かれる、蝶々の叔父であるボンズ(坊主)が、蝶々の結婚に対して「おお神よ!猿田彦よ!」となげく姿を考えてみる。
はたして、『仏教の僧が神道の神の名前を叫ぶはずがない』という意見は、本当に正しいかどうか、判断できるだろうか。
廃仏毀釈が行われている時代の坊主である。
日本に来たことがないプッチーニが作った物語である。
少ない資料、伝聞から作った人物とセリフ。
作者の感覚を想像すると「オー マイ ゴッド」の直訳と見る方が自然だろう。
そこに、当時の日本の状況をあわせれば、「おお神よ!猿田彦よ!」で、そのまんまである。
つまり、日本像として正しいか正しくないかではなくて、「それだけのこと」だ。
逆に、欧米から見たら日本は仏教の国というおおざっぱな印象が支配的であるはずなのに、「猿田彦」という言葉を使ったのは、ちゃんと資料を集めていると見て良いだろう。
もちろん、か細い資料で、不足があるといえるが、当時としては良くやっている。
日本の国家神道や廃仏毀釈という事情は、当時の日本人でも理解できないだろうし、それを、外国から見てわかるはずがない。
それでも外国人が「猿田彦」という名前を知り、使ったというのは、そのこと自体が、当時の日本を知る手がかりになるのではないだろうか。
ついでながら、個人的意見を書く。
蝶々夫人の「坊主が猿田彦と叫ぶのは間違いだ」というのなら、その判断自体が間違いとも考えられる。
廃仏毀釈の世なのだから、「ボンズ」は坊主ではなく「神主」である方が良い。
蝶々夫人の原作に修正を加えると言うのなら、よほど歴史と宗教を研究した方が良いと思うのだが、どうだろうか。