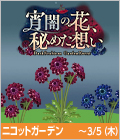犀川先生質問です
- カテゴリ:日記
- 2010/07/02 00:15:14
日頃から、頭に思い浮かぶことはいろいろあるのだが、そのなかで、知識のある人に教えてもらいたい疑問というのもある。
それらの中には、「この人に聞いたら面白い話しが聴けるかな」と人物を思い浮かべることもある。
今回の記事は、そうした日々思ったことをいくつか合わせたものです。
話しの下地は、森博嗣の小説を読んだ『感想』と思って読んでもらえれば、わかりやすいと思います。
-----
僕は、街を歩いていて、ときどき、どうして現在の街が、今の姿に至ったのだろうかと想像する。
この疑問に答えてくれそうな人として、犀川先生を連想する。
犀川創平(さいかわそうへい)は、森博嗣の小説に登場する、大学の助教授だ。
建築学を研究している。
小説では、研究そのものの描写は少ないのだが、どうやら、専門は都市の「変遷」のようなことらしい。
建築物の構造ではなく、街の構造。
そして、その変化が研究テーマ。
たぶん、簡単に言えば、中学校などで習う「川の周辺に街ができる」というようなことを、深く考察するのである。
-----
さて、僕が今、犀川先生に聞いてみたいこと。
「国家は短命なもので、数十年も維持できずに崩壊する例も多い。長くても、李氏朝鮮の約五百年だろう。なぜ、国は破綻するのだろう」
とりあえず、漠然とした疑問を言葉に変換してみた。
「質問する相手を間違ってるよ。それは僕の専門外だ。政治や戦争のことなら、そうだね、社会学や文化人類学の先生に聞くことだね。もしかして君の場合は、民俗学かもしれないな」
犀川先生のなかでは、たくさんの言葉が思い浮かんだようだが、ほぼ全てを保留して、最適な回答だけ発音したらしい。
「あ、いえ、犀川先生に聞きたいんです」
「それは、国を思想としてみるのではなく、インフラなどの構造として見る。ということでいいのかな」一息ついてから、言葉を続ける。「一般的な話し言葉で、広義での社会学や、数理社会学なら、たしかに僕の研究に近いかもしれないね」
犀川先生は、僕には補足が必要だと考えてくれたらしい。
息をついたから、タバコでも吸うのかと思ったが、そうはしなかった。犀川先生は、難題を考える時はタバコを吸うことが多い。つまり、僕の質問は、煙草を吸うほどのものではない、ということだろう。
「例えば、街は規模が大きくなると、いずれは飽和しますよね。平地の面積だったり、水の供給量だったり。
それに、街を作っている最中は楽しいかもしれないけれど、一度完成すると、道が狭いとか、不満が出て来る。
デザインを修正すれば、機能が改善するのはわかっていても、改修工事は面倒だ。
新陳代謝、って言えばいいんですかね、飽和すると、代謝が滞るんですね。
それが理由で国が破綻する。と考えてはいけないんでしょうか」
「君は、まず疑問の本質を整理した方が良いね。物事は多面的だから、疑問も多面性を持っている。煩雑な情報を並べただけでは、必要な境界条件はわからないよ」
「えっと、ですね。
人間も、精神的なものと、肉体的なものがありますね。性格が良いからと言って、健康か病弱かとは直結しない。しかし、緩やかに関連している。
国も、政治や思想と、土地と構造の面がある。
両者は関連しているけれど、都市の工学的側面から国の寿命を量ることが可能なのではないでしょうか」
「そうだね、古代都市にはそうした面がある。現代は条件が複雑だけど。そうだ、それを君の卒論のテーマにしたら」
-----
と、いうわけで、現実の僕としては、ここから先を、犀川先生に教えて欲しいのである。
残念ながら、犀川先生は架空の人物なので、聞くことができない。
いや、現実の人でも、直接質問することはできなくて、本を読むことになるんですね。
結局、想像だろうが現実だろうが、
「自分で調べなさい」
と言われるんだな。