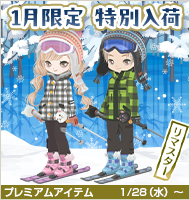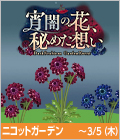ものがたりは完結する
- カテゴリ:テレビ
- 2010/07/16 23:58:35
人の暮らしと言うのは、節目はあっても、明瞭な終わりは珍しい。
そもそも、人間は産まれてから死ぬまで、連続して生きているので、その行為に完結が在っても、生活が完結する訳ではない。
その時々で、「仕事」が完結したとか、学校を卒業したとか、そんな「終わり」があるだけだ。
一方で、「話し」は完結させなければならない。
日常の会話でも、演説でも、締めくくりをつけないと、意味が不明瞭になる。
それは、創作物でも同じ。
小説やドラマ、映画でも、完結するから、意味がはっきりする。
小さな子供がときどき思う疑問。
テレビ番組が「最終回」を迎えてしまうこと。
なぜ終わってしまうのか、終わらなければ良いのに。
これは、子供にとってテレビ番組は「友だち」と等しい存在で、「物語」「誰かの意見」といった捉え方を、まだ知らないから。
子供の頃は、物語の締めくくりかたで、その話しの中にある意見や意味が決まることを知らない。
逆に、大人になると、結末が重要になる。結びが上手なものほど、良い作品だと評価するようになる。
ながながと続いたままだと、不満になる。
飽きても来る。
実は、子供より大人の方が飽きっぽいことも多い。
-----
さて、ここまでの話し、実は、「ハウルの動く城」という映画に意味があるかどうか、という疑問を書いているのでした。
宮崎駿監督が明言していることに、「起承転結の無い映画を作りたい」という言葉がある。
「もののけ姫」は、それらしい雰囲気が在るが、まだ、物語の展開に起伏を付けるように意識している。
そえが、「ハウルの動く城」にいたって、そうした構造を捨てている。
これは僕の想像、というか、僕の個人の意見なのだが、
「本物の人生に、映画のような起承転結は無い」
だから、
「人の心、人生を物語に描くとき、起承転結に捕われずに表現できないか?」
と、思う。
宮崎駿も、そう感じているのではないか。
物語の定型で、登場人物がいい人だったり、悪役だったり、明瞭に描かれるものだが、本当のニンゲンは、良いも悪いも、表裏一体だ。
本当の人間の姿を描くには、定型を離れなければならない。
こうした意図は、もののけ姫の登場人物も、気は悪くないがわがままだったり、がさつだったりするところに見える。
「ハウルの動く城」は、登場人物が、正義の味方でもないし、悪役でもない。
しかし、人として、身勝手やわがままをみせる。
結局、「ハウルの動く城」には、はっきりとした形が無いのである。
さて、困った。
定型を拒否した映画でありながら、最後の最後に、「ハッピーエンド」にして終わらせてある。
キスして終わり。
カブなんか、カブの側が勝手に好意を抱いているのであって、その相手からキスされたからと言って、呪いが解けるというのは、都合が良すぎる。
なぜなら、片思いだから。
変な、動くカブのかかしに想いをよせる人なんて現れるはずも無く、つまり、永久に解けない呪いのようなものだ。
なぜ僕がそのように主張するかというと、宮崎駿は、呪いや魔法について、実際の人生の中で出会う出来事や、それに対する人の考え、気持ちなどを、ファンタジーの形に変えたはずだからである。
ソフィーは老婆に変えられたが、それは、ソフィー自身が「呪われた」「自分はダメなニンゲンだ」と思い込んでしまったのであって、本当の心の奥底が、どんな人間か、何者であるか、心のありようまでは、誰にも変えられないのである。
だからこそ、映画の中で、場面場面で、ソフィーの姿は違った描きかたをされる。
本人の心の問題が、表面に現れている。
ならば
カブは、カブだけが簡単に、ただ見かけの形が変わるというのは、映画全体の魔法の表現と矛盾するのである。
そして、心の問題、答えのでない問い、それら、終わりの無い問題を描いたこの映画は、「はっきりとした答えは無い」と言いながら、でも、娯楽映画として「ハッピーエンド」と言う形で、明瞭に完結させてしまったのである。
(ちなみに僕は、カブはそのままで良かったし、戦争が終わらなくても良かった。むしろ、あいまいに、ソフィーとハウルは、人生の節目を迎えたけれど、じゃあ、これからどうしようか、という形で終わらせれば良かったと思っている)
-----
表現の中に、一貫性のある物語を、観たいなぁ。
って、この一行を書くために、ずいぶんたくさんの前置きを書いたな。。。