虫が少ないし小さい
- カテゴリ:ニュース
- 2010/09/01 22:50:02
お題の「今年の夏」ですが、自分の見る範囲では、虫が少なかった。しかも、今でも小さい。
たぶん、春の雪がいけなかった。
虫が出始めた3月に雪が降った。それで、越冬した卵やサナギが死んでしまったのではないか。
単純に、寒い時期が長引いたのなら、越冬できたはずなのに、一度暖かくなった後に、雪が降った。
羽化やふ化の直前になってしまった後では、越冬の状態が終わってしまっている。そこへ雪が積もってしまった。
僕が見て憶えている異常では、ツツジの花がうまく咲かなかった。
つぼみが大きくなって、開く寸前に雪が積もったので、花びらの先が凍ってしまい、咲いた時にはすでに、花の周りが萎れてしまっていた。
雪が降った時点で小さかったつぼみは、一度、成長が止まって、再び大きくなったので、ツツジの花は、最初に萎れた花が咲き、そのあとしばらく間があいて、もういちど咲いたような感じだった。
そんな状態なので、虫にとっても、住処であり食料である植物の状態が、いつもの春とは違ったのではないか。
チョウなど、夏の間に何世代か繰り返す虫がいるが、これなどは、今年の最初の親になるサナギが死んでしまったので、第一世代が少なくなってしまった。
そして、夏を通して少なかった。
九月になった今、ようやく見かけるくらい、増えるのに時間がかかった。
たぶん、虫によって影響の出かたが違うので、虫の世界のバランスは、例年と違っているはずだ。
もうじき秋になる今でも異常を感じるくらいなので、来年の春に影響を残すだろう。
来年はどうなるのかな。





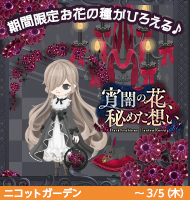














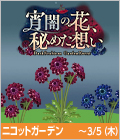







虫のふ化や、羽化、あるいは産卵やサナギになるための条件は、温度の積分などで発現することがわかっています。春になり、一定の温度まで気温が上がる日が、何日間か続くと、体が変化するスイッチが入る。
この温度と日数は虫によって違うけれど、ふ化などのカウントダウンをおこなうのは同じ。
これで、冬に偶然、暖かい日が一日あっても、それだけではふ化しないし、充分、春になってからふ化することになる。そのことで、毎年少しずつ違う条件に対応できる。
ここから、温暖化が進んでも、ふ化のタイミングがおのずから調整されて、適応できるだろう、という予測ができる。
それを映画は説明したのだとおもう。
しかし、実際にはそれほど単純ではなく、細かいことはわかっていない。
また、鳥類は、日常的には決まった虫を取って食べるが、どうしてもその虫が見つからなければ、過去に食べたことのない虫でも食べることがある。
これは観察の例が少ないので、細かいことは不明だけれど、実は食性は思いのほか自由なのかもしれないと考えられている。
多様性についての研究が進まないので、実際にどうなるかはなんともいえませんねぇ。
鳥類の次は哺乳類。地球は早い未来虫の楽園とかすであろう・・という事でした。
温暖化にそって生育スタイルをかえて来た虫たちにとって今年の異常気象は大打撃だったのでしょうね・・。