さいきん動画を見るようになった
- カテゴリ:日記
- 2010/10/06 23:58:13
WiMAXにする前までは、動画なんて見てられなかった。
それで、動画を見るという発想がなくて、WiMAXにしてからも、しばらく見てなかった。
それが、、、
(あ、「それ」が連続する文章になってしまった。
もっと美しい文体を目指さねば!)
(気を取り直して)
それが、「みちびき打ち上げ」のストリーミングをきっかけに、動画が見られるんだ、と気がついた。
でも、この動画と言うのは、静止画に比べても厄介なもので、
なにが厄介って、ニンゲンは厄介なもので、
動画を作った人が公開している場合より、なにか他のところから動画を入手して、それをアップロードしていることが多い。
昔のビデオだったり、今のDVDだったり、ともかく、基本的にはロイヤルティを侵害しているものが多いと思う。
ここで悩むのである。
ロイヤルティの侵害と言ったところで、本当にそれが悪質かどうかは判断が難しい。
古い芸能人の写真など、買おうと思っても売っていなくて、ネットで見る事ができたら、嬉しいのである。
それが、ロイヤルティの侵害であったとしても、現実的には、権利者の芸能人にも特になる場合もあるし、見た人も得だ。
もちろん、ひどい侵害も在るのだが、ともかく、道具と行動、という形だけをとって見ると、善悪には分けられない行為。
歌手の古いプロモーションビデオなど、買えないのだから、ネットで見るしかない。
幸い、音楽関係は、著作権管理団体へ、動画サイトからロイヤルティが払われているはずだから、侵害ではない場合が多い。
そこが救い。
でもやっぱり、怪しいものが多い。
「見る」立場の人間としては、できれば、一番元の、アーティストに、きちんとお金を払いたい。
払うべきお金を、払うべき人へ、渡したい。
これが経済のもっとも基本だと思うんだけどな。
ネットだとそれが難しいね。



















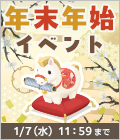










それに、ネットが普及してから、「間に入る人」が集金するようになって、誰にお金が入るのかわからなくなってしまったのが困るところ。
日常的に、「商業利用権」のことを「著作権」と言ってしまうのが誤解の元のような気がする。
「本にする」「CDにする」そうした商売の権利だから、作者とは別の人へ買い取られていてもわからない。
「著作者人格権」の理解が世の中に広がるとよいと思う。
キチンと作り手に還元されるシステムがあれば良いのでしょうけど、色々難しいですね。
映像や音楽でも、ダビングがし難いと言っても、詳しい方なら出来ない訳でもないですし・・。