娯楽でなければならないのだろうか
- カテゴリ:映画
- 2010/11/14 23:31:33
テレビで、映画「最高の人生の見つけ方」を観た。
この物語を作ろうとした人たちの、誠意は疑わないし、言ったことも疑わない。
ただ、描かれた「具体的なできごと」について、こうした話しにしなければならないのだろうか、と心に引っ掛かる。
僕がここで言いたい「具体的なできごと」というのは、映画の中で、例えばSFなら、光速を超えてワープで星間飛行をおこなうとか、昔話で、桃から赤ちゃんが出てくるとか、そういう部分。
SFでも、物語の主題によって、現実的な科学技術を中心にして、「光速」などという遠い未来でも実現できるかどうかもわからない技術は排除することもあるし、積極的に、タイムマシンでも、万能なスーパーコンピュータでも、登場する映画もある。
昔話でも、夢物語を描く場合もあれば、現実を描く場合もある。
では、「最高の人生の見つけ方」はどうだろうか。
末期ガンで偶然同じ病室に入った男性が、友人になり、余命宣告を受けて、残りの時間、人生を楽しんでみようとする話しだ。
二人は旅に出る。
一人の男が資産家だったので、金に不自由することなく、「やりたいことをやろうじゃないか」と行動に移したのである。
さて、これは娯楽映画である。
だから、スカイダイビングをしてみたり、エジプトでピラミッドを眺めたり、季節外れのチョモランマへ出かけたりもする。
制作者側の都合のようなものを考えると、ようするに、娯楽映画の華やかさのために、主人公の一人を資産家にしたのである。
この映画と同じ趣旨で、もし、
「近所のレンタカー屋に新型の車が入ったから、借りて乗り回してみた」とか、
「ちょっとだけ遠出して、太平洋に沈む夕日を観た」
「医者の言いつけを無視して、高級レストランのコースを食べた」
なんて物語にしたら、
どうなるのだろう。
娯楽映画として成立しないのだろうか?
この映画では、主人公は旅行を通して、日常に押しつぶされていた心がほぐれて、家へ帰る。
映画の中に、大金を使った世界旅行という「仕掛け」を用意しなければ、映画は成り立たないものなのだろうか。
繰り返すが、この物語を作った人の誠意は疑わない。
良い映画か悪い映画かと問われたら、良い映画の方へいれる。
でも、どうしても、
物語が「金持ちの道楽」から抜け出せなくなっているように感じる。
SFのタイムマシンのように、ヒューマンドラマの仕掛けが必要なのだろうか。





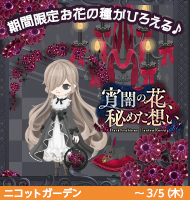

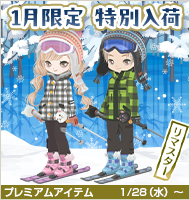












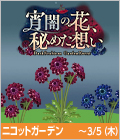







「良い映画」ってなんだろうかと、ときどき思う。
スピルバーグの「シンドラーのリスト」や「プライベートライアン」などは、良いからといって、気楽に見られるものではない。
精神的に強い状態でないと、二時間見続けるのも大変。
そうした映画は、良い映画だからといって、大勢の観客が見てくれるとは限らない。
じゃあ、「みんなが親しみ易い形に」とした場合、良い映画が、たくさんの人に見てもらえるが、本来の形から変わったものが、どれだけ良さを残しているのだろうか、という疑問も産まれる。
「最高の人生の見つけ方」は、まず、たくさんの人に親しんでもらおうという意図がはっきりしていると思う。
その点では、納得できるものだった。
もしかしたら、もっと極端なコメディにしてしまうのも、ひとつの方法かもしれない。
へんにリアリティが強いので、金持ちの強引さが、生々しくなってしまったようだ。
-----
森見さんの小説は、自分の中で忘れかけていた、使わなくなった言葉のリズムを思い出させてくれるようで面白い。
内容も、ふだん閉じ込めていた自分が、解き放されるよう。
古本市の神が活躍するような発想は、つい、日常の中で、考えないようにしてしまっている。
ん〜、そういえば、子供の頃は他人の家の犬と仲良くするのが平気で楽しいのに、大人になったら我慢してしまうのと似てるかな。
森見さんの小説を読むと、その我慢をわすれるみたい。
ブログ広場の映画カテゴリからやってきました。
映画カテゴリをまわっていて、この映画に「泣いた」「感動した」という言葉をたくさん見かける中、
れおポンさんの記事がとても印象的でした。
わたしは映画『最高の人生の見つけ方』は観ていませんが
小さな幸せでも、十分幸せだし、
娯楽映画として成立すると思います。
れおポンさんの疑問は正しい気がするなあ。
ちなみに、わたしも最近森見登美彦を読み始めて
『四畳半神話体系』『夜は短し歩けよ乙女』と読みました。
調べたら、著作がけっこうあるようなので、いろいろ読んでみたいと思います。