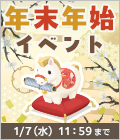科学は行間を読む
- カテゴリ:勉強
- 2011/07/18 20:49:54
「行間を読む」といったら、いつもなら文学を思う人が多い。
具体的に言葉にしてあることではなくて、それらを組み合わせて想像すると見えてくる内容。
そこに、文学の楽しみがあると言われる。
これと同じことを、科学者は日々考えている。
それを、科学に触れない人は、知らない場合が多いのではないか。
ニュートンは、物が動くときの法則性を考え、力学を作った人だ。
飛んでいるボールは、外部から力を与えない限り飛び続ける。慣性の法則。
ビリヤードの玉がぶつかると、転がっている玉から、止まっていた玉へ、ぶつかった瞬間に、動く力が伝わって、止まっていた玉が転がりだす。エネルギー保存の法則。
そんなことをニュートンは考えて、論文にした。
では、論文に書いてあることが全てか?
書いていないことを想像する。
もしも、ニュートンが言うとおりに物体が動くとして、それは、放物線など、いろいろな数学の式に表される。
計算すれば、動きがわかる。
ボールを機械で飛ばすのでも、投げる前に、何メートル先に落ちるか解る。
実際にやってみると、計算とは少し違う場所に落ちるが、それは、機械が設置場所の振動を受けていたり、風の動きが計算に入っていないからだ。
人間には、周辺の状況を瞬時に察知する能力が無いから、計算できない。
じゃあ、神のみぞ知る、空気の動きなど、周辺の条件を知ることができて、現在この世にあるコンピュータよりも、もっと速いコンピュータで計算したら、ボールの動きは解るのか。
大問題である。
理屈だけなら、「計算できるはずだ」という結論になるだろう。
法則が正しいのなら、計算できる。
膨大な量の計算を瞬時にできるのなら、未来が計算で解る。
やはり、大問題である。
未来は決まっている!
ニュートン力学の「行間を読む」と、未来は決まっているということになる。
論文にそのことが直接書いてあるわけではないが、そういう意味になる。
本当に未来は決まっているのか?
決まっていないと感じている人がほとんどだし、それならば、ニュートン力学は学問として不足していると考えるべきなのである。
そうやって、科学者はたくさんのことを考えて、過去の学問を修正、進歩させて行く。
—————
原発事故などで、「科学技術が揺らいでいる」などという表現が聞かれるようになったが、それは、「見える側」「具体的に書いてある側」の問題である。
多くの人、程度の低い学者は、具体的な面ばかり見ているので、間違えた部分、破綻した部分しか見えない。
「想定外」とは何なのだろうか。
その前に「想定」とはどんなことか。
それは、そもそも目の前に無い、具体的ではない出来事を予想し、「起きるかもしれないこと」と「定めて」準備すること。
予想できなかったことや、予想の範囲を超える現象が起きたら、それが「想定外」だ。
「想定」もまた、「行間を読む」のと、本質は同じだろう。
見えていることを組み合わせて、まだ知らないことを読み取る。
やはり、行間を読むことに科学の本質がある。
—————
ところで余談なのだが、ニュートン力学から導かれる、「決定された未来」。
これは、けっこう普通のことだ。
誰だって、眠って、朝目が覚めたら、見知らぬ土地にいる、なんてことは無い。
寝相の悪い子供だって、部屋の反対側に移動するのがせいぜいだ。
未来は、ある程度の範囲で決定している。
ニュートン力学は、理論として不足があっても、十分に、多くの正しいことを説明しているのも事実だ。