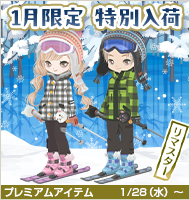ベクレルとシーベルト 3
- カテゴリ:勉強
- 2011/08/22 21:46:33
ウランやプルトニウムのような重い原子に中性子が当たると、α崩壊する代わりに、核分裂して2個以上の別の原子に変わることもある(いま話題のヨウ素131やセシウム137などはこうしてできた)。このとき、中性子が何個か飛び出し、γ線も出る。飛び出してくる中性子は、エネルギーが高いので放射線の一種で、これは中性子線と呼ばれる。この中性子線がほかの核分裂しやすい原子核に当たると、その原子核も核分裂することがある。そうするとそこからまた中性子線が出る。だから、核分裂しやすい性質を持った原子が濃く集まっていると、次々に原子核が分裂して、止まらなくなる。この状態が臨界状態。
放射能って何だろう?
日本語で放射能っていうのは、放射線を出す性質のこと。中国語では「能」と言えば「エネルギー」という意味だから、放射線を出す "性質" のことを「放射 "能"」とは言わず、「放射 "性"」と言う(もちろん中国人でも間違った意味で「放射能」という単語を使う人はいるかもしれない)。英語では radioactivity という。ここに、 -ity という「性質を表す語尾」が付いていることから考えても、「放射能」という日本語訳は、あんまり適切な訳ではなかったかもしれないね。「放射線を出す性質」のことを「放射 "能"」と呼ぶのは、日本独特の言い回しだろう。すっかり定着してしまったから、これを使うしかない。だから「放射線を出す性質」(放射能)を持った物質のことを、時には放射能と呼んだり、あるいは放射性物質と呼んだりすることもあるわけだ。
グレイ
放射線は、物質に当たるとその物質の原子を電離(イオン化)させる作用がある。原子を電離させるとき、放射線のエネルギーがその原子に吸収される。このとき、1kgあたりの物質に1ジュールのエネルギーを与える放射線の吸収線量(ジュール/kg)が1グレイ (Gy)。
電離って?
原子はプラスの電荷を持つ原子核と、そのまわりにあるマイナスの電荷を持ついくつかの電子から成っている。その電子を、原子核のそばから引き離す作用が電離作用だ。
α線は電離作用が強い。つまり、α線が物質に当たると、そのエネルギーが吸収されやすい。逆に言えば、物質に当たると自分のエネルギーがすぐに弱くなって止まってしまう。だから、α線は薄い紙でもさえぎることができる。
β線は、α線より電離作用が弱いので、物質に当たってもα線よりは止まりにくい。β線は厚さ1ミリ程度のアルミの板や、厚さ1センチ程度のプラスチックの板などでさえぎることができる。
γ線は、さらに電離作用が弱い。γ線は厚さ数センチの鉛の板などでさえぎることができる。
中性子線は、水素などの軽い原子の原子核にぶつかると、ぶつかられた相手の原子核は走り出して、それが電離作用を発生する。また中性子線は、重い原子の原子核を走らせる作用は弱いけれど、重い原子核に吸収された直後にγ線を出す作用がある。このγ線には電離作用がある。逆に中性子線は、水素などの軽い原子の原子核にぶつかると自分のエネルギーを失いやすいから、水槽などで中性子線をさえぎることができる。
シーベルト
放射線は、生き物の体を構成している分子やそのまわりの水も電離させる。細胞の中のDNAが電離して壊れることもあるし、電離した水分子が細胞を構成している分子と化学反応して、細胞を痛めることもある。
放射線が生物に与える作用の大きさは、放射線の種類によって違う。この違いを加味した放射線の量(ジュール/kg)は等価線量と呼ばれ、シーベルト (Sv) という単位が付く。 グレイから等価線量を計算するには、放射線の種類別に重みを決めてグレイの値に掛け、それらの合計を出す。重みの具体的な数値は国際放射線防護委員会 (ICRP) が決めている。例えば、α線なら×20、β線やγ線なら×1(つまりグレイと同じ値)、中性子線ならエネルギーの大きさによって異なり、最大で×20。 ニュースで「空間線量率」として出てくる値(シーベルト/時)は、1時間あたりの等価線量だ。
さらにつづく。。。