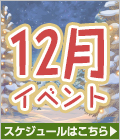米国 vs.イラン、サイバー戦争勃発の可能性は?
- カテゴリ:ニュース
- 2013/01/11 21:05:47
米国の銀行に対する少なくとも過去6カ月にわたる一連の大規模DDoS攻撃の黒幕として、イランが再び名指しされている。銀行を狙ってDDoS攻撃が行われるのは日常茶飯事だが、米銀に対する攻撃の規模と執拗さは、間違いなく異例なものだ。専門家は、「サイバー空間で始まった紛争が、世界初の継続的なサイバー戦争に変わりつつある」と指摘している。
HSBC、Bank of America、JPMorgan Chase、Citigroupといった各行が攻撃され、金銭的な被害を受けている。多くのインターネット・バンキング・サービスで、攻撃のせいで重大なサービス障害がたびたび発生している。
New York Timesは1月8日付けの記事で、米国国務省と商務省の元幹部であるジェームズ A. ルイス(James A. Lewis)氏が、「米国政府内の認識では、イランがこうした攻撃の黒幕であることは疑いの余地がない」と語ったと報じている。
ルイス氏をはじめ、米国のメディアに登場する事情筋は、攻撃の規模(2007年にエストニアで通信遅延を発生させたロシアによる悪名高い攻撃の数倍と言われている)だけでも、それが国家の仕業であることが示されていると主張するにとどまり、新たな証拠は提示していない。
イランは2012年9月、これまでにこの件について述べた数少ないコメントの1つの中で、攻撃を行っている事実はないと否定した。しかし、米国外でもこの否定を信じる人はほとんどいない。
イランは、2007年から受けてきた一連の高度な攻撃の報復を行っていると見られる。これらの攻撃は、巧妙さと複雑さから見て、米国とイスラエルの差し金としか考えにくいとの見方が多い。
2010年に出現したマルウェア「Stuxnet」による攻撃がその1つだ。それ以降も何度も攻撃が仕掛けられており、その中には、さまざまな機能を持つ高度な標的型マルウェア「Flame」を使って2012年に行われたものが含まれる。どちらの攻撃も、イランの原子力産業と軍を標的にしているもようだ。
イランも米国も一歩も引かない姿勢を崩していない。両国の戦いは今後、深刻な事態に発展していく可能性がある。
http://www.computerworld.jp/topics/563/206098