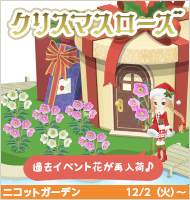ついにベールを脱いだ米国の第6世代戦闘機
- カテゴリ:日記
- 2021/12/05 14:30:36
長い間秘密のベールに包まれていた米空軍の「次世代航空優勢(NGAD:Next Generation Air Dominance)」プログラムが、徐々に姿を現してきた。
NGADプログラムとは、F-22の後継となる次世代戦闘機を含む「ファミリーシステム」の開発を目的とした米空軍のプログラムのことである。
一般に、次世代戦闘機がNGADと呼ばれている。
NGADプログラムには航空優勢が含まれているので、航空優勢について簡単に説明する。
航空優勢とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態のことであり、これを確保することにより、その空域下で海上作戦や陸上作戦の効果的な遂行が可能となる。
仮に航空優勢を失えば、敵の航空機やミサイルなどにより、飛行中の航空機はもとより、地上部隊や航行中の艦船なども攻撃を受けることになる。
このため、戦闘機が作戦空域に迅速に展開し、より遠方で、敵の航空機やミサイルによる航空攻撃に対処できる態勢を整えることが、極めて重要となる。
このような戦闘機の重要性に鑑み、各国とも戦闘機の開発等に注力しているのである。
さて、NGADプログラムは、2010年代初頭に開始されたが、長い間、次世代戦闘機の設計概念などが公表されず、新しい戦闘機の開発を断念したのではないかと見られていた。
ところが、2020年9月、突然、ウィル・ローパー空軍次官補(調達・技術・兵站担当)(当時)は、NGADの実証機が、すでに飛行していたことを明らかにした。
そして、2021年6月、米空軍参謀総長のチャールズ・ブラウン大将は、インド太平洋地域での運用を考慮したNGADはF-22よりも大きなペイロード(ミサイル・爆弾の搭載量)と航続距離を備えると証言した。
また、同じ公聴会に出席していた航空戦闘コマンド(ACC)司令官のマーク・ケリー大将は「NGADはインド太平洋地域向けに大きなペイロードと航続距離を備えたタイプと比較的戦場までの距離が短い欧州向けのタイプの2種類になるかもしれない」と証言した。
以上の米空軍幹部の発言(発言の詳細は後述する)などから、米空軍の次世代戦闘機、すなわち第6世代戦闘機は、F-22より大型の航続距離の長い戦闘機で、インド太平洋地域向けと欧州向けの2つのタイプが計画されていることが明らかになった。
だが、第6世代戦闘機が有人機、無人機または有人・無人の両用戦闘機であるかについては、米空軍幹部からは含みを持たせた発言がなされている。
以下、初めに戦闘機の世代区分について述べ、次にNGADの開発動向について述べ、最後に日本および主要国の次世代戦闘機の開発動向について述べる。
1.戦闘機の世代区分
(1)戦闘機の戦い方の変遷(出典:防衛省「次期戦闘機の開発」)
戦闘機同士の戦い方(「空対空戦闘」)は、ミサイル技術や情報共有のためのネットワーク技術の進展などにより大きく変化している。
戦闘機同士が近距離(目視範囲内)で格闘戦を行う「ドッグ・ファイト」から、目視できない遠方からミサイルを発射・回避し合う戦い方が主流になった後、現在は、ステルス性による秘匿と多数の高精度なセンサーからの情報の融合が重要となっている。
世代の違う戦闘機間での戦闘では、新世代機が圧倒的に優位と言われている。
(2)戦闘機の世代区分
ジェット戦闘機の「世代区分」は、ロッキード・マーティン社が自社の製品であるF-22やF-35を「第5世代」と呼称し、他社の競合機を「第4世代」とすることで差別化を図るために作り出した言葉であるとされる。
直感的に理解しやすい区分けだったこともあり、戦闘機の「世代」なる用語は世界的に定着した。よって、戦闘機の世代区分に明確な基準はない。
●第1世代戦闘機とは、1940年代に登場した黎明期のジェット戦闘機をいう。
1950年代までの亜音速ジェット戦闘機がこれに分類され、超音速ジェット戦闘機は続く第2世代ジェット戦闘機以降に分類される。
代表的な第1世代戦闘機としては、米国の「F-86」、ソビエト連邦の「MiG-15」などが挙げられる。両者は朝鮮戦争での空中戦によって広く知られている。
●第2世代戦闘機とは、1950年代に登場した初期の超音速戦闘機をいう。
米国の「F-100」は、史上初の実用超音速ジェット戦闘機である。これ以降に登場し、1960年代まで運用された超音速ジェット戦闘機が第2世代として分類される。
代表的な第2世代戦闘機は、米国の「F-104」、「F-105」、「F-106」、ソ連の「MiG-19」、「MiG-21F」 、「Su-7」、「Su-9」、「Su-11」などをいう。
1960年代より徐々に第3世代へと移行するが、その区別は曖昧である。
ちなみに、1956年に配備の始まったサイドワインダー(空対空赤外線誘導ミサイル)を装備した「F-86」が1958年の台湾海峡における金門島砲撃戦時の大規模な空中戦で中国空軍の「MIG-17」を撃墜した戦果をあげた事例などから、「ミサイル万能論」が唱えられた。
●第3世代戦闘機とは、主に1960年代に登場した超音速戦闘機をいう。
先の第2世代戦闘機との区別は曖昧であるが、マルチロール・レーダー誘導ミサイル搭載能力・夜間戦闘能力を有するものが第3世代として分類される。
代表的な第3世代戦闘機は、米国の「F-4」、「F-5」、「F-111」、ソ連の「MiG-23」、「MiG-25」、「Su-15」、中国の「J-8」、「JH-7」、フランスの「ミラージュ F1」などをいう。
●第4世代戦闘機は、1980年代から運用が始められ、現在まで運用されている高度な多用途性能・長距離広域探索レーダー・同時交戦能力などを有するマルチロール機をいう。
代表的な第4世代戦闘機は、米国の「F-14」、「F-15」、「F-16」、「F/A-18」、フランスの「ミラージュ2000」、中国の「J-10」、「J-11」、ロシアの「MiG-29」、「MiG-31」、「Su-27」などをいう。
●第5世代戦闘機とは、おおよそ2000年代から運用が始められたステルス性能を有する戦闘機のことをいう。
ロッキード・マーティン社は、第5世代ジェット戦闘機の特徴を「センサー・フュージョン」・「ステルス性」・「(第4世代に勝る)性能」・「より進歩した整備・保守性」と定義している。
代表的な第5世代戦闘機としては、米国の「F-22」と「F-35(A、B、C)」、ロシアの「Su-57」、中国の「J-20(殲20)」などである。
ただし、J-20については、他のステルス機が有していないカナード翼を有している。カナード翼は運動性能を向上させるが、反面ステルス性が損なわれるという指摘がなされている。
●第6世代戦闘機
日・米・中・ロなどは、2030年から2035年の実用化を目指し次世代戦闘機/第6世代戦闘機の開発を競っている。
第6世代戦闘機には、第5世代を超えるステルス性能、指向性エネルギー兵器の搭載、クラウド・シューティング能力および有人戦闘機随伴型の無人機との協働などの幅広い能力が求められている。主要国の開発動向は後述する。
以下略
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/67929