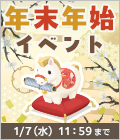戦争と日常
- カテゴリ:映画
- 2009/10/26 23:33:04
何年ぶりだかわからないくらいに久しぶりに「ゴジラ」を見て、ふと別の映画を思い出した。
「戦場のピアニスト」
この映画を見て一番感心したのは、日常生活を描いたことだ。
物語は、ユダヤ人ピアニストの境遇と、最後にそれを助けたドイツ将校の話なのだ。
この物語に感動が在るとしたら、戦争という困難の中にも、人の優しさが存在しうるということだろう。
たぶん、多くの人が、そこで涙を流すだろう。
でも、僕は、そこには感動しなかった。
映画が人を描く時に、善を描く時に、当然の物語だと思った。
こうした物語は、映画の技術的仕上がりが悪くても、感動できるものだ。
この映画を傑作にしたのは、物語の結末ではなくて、そこへ至るまでの、戦時下の生活を描いたことだと思う。
映画の始まりでは、画面に映る人たちは、戦争が起きていることを知っているし、それが決して良い状態ではないことも知っているのだが、まだ普通の生活を送っている。
そこから、人々は実際の戦闘の中に巻き込まれてゆき、困難が深くなってゆく。
この戦争の中での生活を描いたことが、「戦場のピアニスト」の価値だと思う。
「ゴジラ」という映画が、戦後間もない日本人の生活を描いたものだと、今になって初めて気がついたのだ。
太平洋戦争は、そこに至るまでの政治はともかくとして、戦闘行為そのものは、日本が積極的に起こしたものだ。
そんな国の人間が、ただ戦争反対を叫んでも意味がないだろう。
かと言って、当時のアメリカとソビエトのにらみ合いの中で、敗戦国として単純にアメリカの下僕になってはいけない。
日本人の中にも、太平洋戦争に反対した人もいるし、敗戦よりも、終戦の事実に喜んだ人もいる。
そうした日本のあり方について、戦争映画ではなく、ゴジラという水爆の被害者を描くことで、表現したのだと思う。