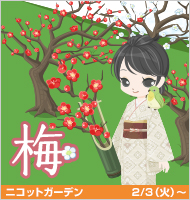THE ALFEEとGAROのこと
- カテゴリ:音楽
- 2024/05/27 09:50:31
このテーマで以前から書きたかったのです。
まず。「日本を代表するロックバンドは?」と訊かれたら何と答える?
ヤザワ? X JAPAN? BOOWY? B'z? それぞれ一理も二理もあるけど…。
自分の嗜好を度外視すると、私はかなり本気でTHE ALFEEと答えたい。
GSがニューロック・フォーク・歌謡曲へと分かれていき、
欧米に追随した時代の息吹を未だに持ち続け活動している。それだけで凄い。
しかもメッセージは初期からポジティブ、元気・勇気ソングばかり。
高見沢氏の個性が強く出てるんでしょうけど、肯定的世界観は普遍です。
21世紀の人々にも通ずる、前向きで勇気づける楽曲の数々。
音楽的にも時代の音を随時消化し取り入れてるけど、
本質的な音楽観がまったく揺らいでいない。愛・平和・勝利。
ウッドストックの息吹を今でも信奉してるわけです。これが現代に求められてる。
親族や女友達でハマった者がいるので、70年代から80年代のはリアルで聴いた。
私の世界観や目指す音楽と正反対だから全く受け入れられないし、興味もない。
だが彼らの素晴らしさというのも評価しないわけにはいかない。
坂崎氏のギターの匠ぶり、桜井氏の若干黒っぽい歌唱も素晴らしいし、
コーラスの見事さはスターダストレヴューと双璧ではないか。
大嫌いな高見沢氏のトレモロアーム使いも、あそこまで貫けば芸である。
ロックとしての視点でTHE ALFEEを論じる価値も十分あるのです。
不失者もマキOZも外道もシナロケもじゃがたらも大好きな私ですけど、
好みではないTHE ALFEEは、今の日本を代表するバンドだと心底思う。
さてこの3人がGAROの後輩であることは良く知られてますが、
彼らの活動はある意味、GAROが果たせなかったことを実現してるようにも思う。
そんなわけでGAROの話題に移る。こちらは本気で好きなバンド。
その昔、日本語ロック論争という業界マッチポンプ的イベントがあり、
内田裕也さんの敗北で終わったのは歴史が証明してるわけです。
はっぴいえんど/ティンパンアレイ(どっちも大嫌い)が日本大衆音楽を支配した。
この戦いって結局、ロック=マイノリティか否かという争いなわけでして、
商業音楽としてのロックを考えれば、売れたモノが勝ち!に決まってます。
英詩に拘る人々の敗北は必然でした。少々補足しましょう。
当時、なぜ英語に拘ったのか? カンタンです。「ワカラナイから」!
乱暴な話ですけど、意味ワカンネェからカッコいいんだぜって思想です。
古の暴走族の竹槍マフラーやゴッドファーザーホーンとオンナジ。
幼少からリスニング能力鍛えた英語ネイティブにはワカランでしょう。
Ronk'n Rollじゃないんです。ロケンローだったからカッコよく感じた。
実は『理解不能な衝撃≒アート』という、音楽の本質に関わる問題。
さて、GAROはカバー以外、日本語で演ってました。
ヒット曲が出た幸運で当時としては予算が潤沢に使え、
日本語ロック論争の勝者となった連中をスタジオに呼んで使った。
ミッキーカーチスさんの意向も強く、ご本人たちはかなり不満であった。
特に日高富明氏はロック気質の人だし(逸話多し)かなり反発したらしい。
ですが結果的に、はっぴいえんど/ティンパン人脈を活用したことも幸いした。
阿久悠が全ての詩を書いたトータルアルバム『吟遊詩人』がいちばん好き。
まず阿久悠の詩が素晴らしい。彼の実体験や心象に基づくであろう、
プライベートな鬱屈が横溢し、70年代の空気が封じ込められている。
編曲は全て松任谷正隆。荒井由実のアルバムと並べても遜色ない仕上がり。
タイコは原田/上原、ベース細野、ギター大村/伊藤銀次、テナー村岡、
コーラスはシュガーベイブにハイファイセット……贅を尽くすにも程がある。
作曲は大野/堀内/日高が担当し、それぞれメインボーカルを務めてます。
3人の個性が出ていて、どの楽曲も聴きごたえがある。
白眉はラスト曲の『吟遊詩人』。1stの名曲『暗い部屋』と双璧です。
リリースは75年の6月。同時期の名盤といいますと、
ジョニミッチェル『夏草の誘い』スティーリーダン『うそつきケイティ』
ザ・バンド『南十字星』イーグルス『呪われた夜』等々、山ほどあります。
並べて聴くと趣がある。特に、アメリカの音楽がウッドストックに幻滅し、
アメリカンであること、伝統への回帰を志向しはじめたのに対し、
『吟遊詩人』には全共闘敗北後の絶望、諦念と投げやりさが濃厚。
THE ALFEEはGAROのこうした活動や葛藤を間近で見ていた。
様々な思いがあったんでしょう。GARO亡き後、THE ALFEEは、
GAROを参照しつつも、ある部分を切り捨て、自分たちの独自性を加えた。
GARO唯一の生き残りである大野氏は商業音楽界で活躍しており、
THE ALFEEとも仲が良い。これはGAROの精神の継承でもあるが、
日高氏の個性だった「かそけき捨て鉢さ」はそっくり失われてしまった。
GAROの事実上のラスト曲は『青春の旅路』という名バラード。
バンド解散に伴い、大熨氏は二人の猛反対を押し切り、
「これからは互いに気疲れすることも無くなるだろう」と歌った。
こうした感情の迸りこそが、私の好きな時代のロックの特徴だと思う。
THE ALFEEは未だに仲睦まじい。彼らのやりとりは漫談なみに面白い。
これが21世紀にふさわしいロックだ。たまにラジオ聴くと思うのです。