ハーブティ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/02/09 02:14:21
・私は緑茶が好きだ。
ちゃんとした日本茶の老舗で購入すると馥郁(ふくいく)たる香り、口に含むと甘さと爽やかさが口中に広がり のどごしすっきりの茶葉に出会うことができる。
もちろん 買ってきた日本茶は、茶筒に入れてほぼ密閉状態で保管しないといけないが。
・その一方で 紅茶も わりと好き
でも 紅茶って どんなにおいしい紅茶でも 単体では今一だったり、飽きやすくて・・
というのも紅茶葉は 開封したとたんに味と香りが落ちていく。開封後も 密閉状態を維持して家庭内で保管しつつ飲み切るのは案外むつかしい。
なので 開封後の紅茶葉の 使い終わりのころは、砂糖とかプラスアルファで変化をつけたくなる。
・その一方で ハーブティなるものも 一通りも二通りも試したが、あれも 香りは良いが、開封後の味の変化が 紅茶よりも早い。
密閉だけでなく 保管中の室温の変化も受けやすい
しかも 毎日飲みたいものでもないので、
一度 購入すると、ハーブ本体の微妙な変化に合わせて
(飲むために)いれるときの微妙な調整が必要となる
まあ、開封直後に飲むときでも、香りを中心にブレンドしちゃら、味のほうは 蜂蜜とか紅茶にまぜた方が飲みやすいとは思うけど。
・しかもハーブは微量な加減が味の決め手
要は 個性的だからこそ スープの隠し味には適していても
飲み物にするには ついつい「入れすぎ注意」の罠に陥るのだ。
なので 粉末だと 昔のファーストフードのコーヒーに添えられていたかき混ぜ棒の代わりについていたプラスチックの小さじ1杯より少なめ(用は 茶さじ1杯の少なめ つまり耳かきの先ですくえる程度の量)がよいのだが・・
基本的に 私は 元の形状がはっきりわかる乾燥させただけのやつが好きなので(本来の味と香りを確かめやすいから 製品の品質も確かめやすいしw) そうすると 少量飲みたいときの入れ方が・・・
そんなこんなで 少量おいしい ブレンドハーブティを飲みたいのに・・おいしく入れたい時に作りすぎるぅ~ という悩みがあった。
というのも メインになるハーブを引き立てるように2・3種類ブレンドしているのが好みだったので。
・で 最近思いついたのが、
茶こしにハーブを少量入れる
急須または紅茶ポットに その時飲みたい紅茶を入れる
ポットからカップに紅茶を注ぐときに
ハーブ入りの茶こしを使って ハーブの中を紅茶を通過させる
その際 一煎目 二煎目の 茶葉・ハーブの開き加減や
その時の気分で、 ハーブを通過させる紅茶の量を加減する
(つまり 茶こしを通すか遠さないかを加減する)
・このやり方だと、ハーブの量の加減が 簡単でしたw
ついでに言うと 開封後時間がたつにつれて香りが薄くなる紅茶葉の物足りなさを ハーブの香りで補うにも このやり方がちょうどいい(味より先に香が先に失せるのが紅茶)
つまり 紅茶の葉も ハーブの葉も 成分が液体に 溶け出すタイミング(湯温も含めて)それぞれみんな違う
なので それらを 一つのポットに入れるとなると味のバランスがむつかしい
だったら ポットと茶こしに分けて、 湯温とそれらが液体に溶出するタイミングを 2段階で調節すればいいじゃん! というわけ。
しかも、香りイメージで脳が喜ぶ刺激と
味わい(こっちは 割と安定したものを私は求める傾向にあり)による満足感の両方を満たしやすい♬
(長年の試行錯誤で 湯温と香りの組み合わせで 出来上がりの味はほぼ予想できるので)
その日の気温も含めた 日々の移ろいの中で 感覚的に手動で調節ww
そして 一煎ごとに わずかに変化する葉っぱたちにあわせた味変・香り変も楽しむ♬
人間 時間にゆとりがあると
いろいろ試す楽しみもあれば
元来が 「手早さ優先」なので
忙しい時の気分転換に パパっと 好みの味と香りで
脳を刺激し 気持ちも穏やかにできる茶の入れ方のルーティン化は
忙中閑ありの彩でもありました。
・その点 ちゃんとした日本の緑茶は、保管中・開封後使いきるまでの味と香りの変化が極力抑えられた製品化(これは 一度に販売・出荷する量も厳選されているからだと思う)
急須も大小決まったサイズと形状で、
誰がいれても 手順さえ守れば間違いのない味と香り
(ただし 昨今は その手順を知らない人が多すぎるけどw)
日本人の知恵と技術の結晶だなと思う。
(その代わり一煎使い切りの潔良さ
家庭用でも頑張って二煎まで
これを手間に思うのが 現代っ子かもw)
・だから ちゃんとした店で茶葉を選ぶと間違いがないのも日本茶なのです。
(ただし 関西限定だけど。
東京の売り子は客をなめてる。 基本が「講釈だけで中身ダメダメ」が東京人の味覚w)
だいたいが 「今日は 甘めで」「今日はすっきりとしたのを」「さっぱり系で」「xxだから(その時期の天気が)蒸し暑いとか 寒暖の差が激しいので帰宅時に飲みたいとか、飲みたいシュチエーションを言う)そういう時に毎日飲みたい」というあいまいな私の希望に合わせて
おすすめの茶葉を選んでくれるのが、私がよくいく いくつかの日本茶のお店だもの。
(決め手は 店員の質。本当の意味で味がわかっている人でないとだめ。舌先三寸の能書きしかいえないやつはダメ)
それも 場合によったら 価格帯の違うものから1種類づつ2種類くらい選んでくれる。(たまに飲むならこっち よく飲むならこっちみたいにw)
新茶などは 基本的に購入後半月 長くても1か月以内に飲み切るのがおすすめだと少量入りを勧めてくる。
春先は 九州産から始まって京都から静岡産まで 順番に「新茶の旬」が変わるらしい
当然 産地によって新茶の味わいも異なる(笑)
あるいは たびたび買いに来れないので長く楽しめるものをと言えば それなりのものを保存方法も含めて選んでくれる。
(多分 仕入れたてのやつと味持ちの良さを勘案して。
↑
周りにほかの客がいないときにそこまで ぶっちゃけて説明してくれたことがあったから。)
なんかこう 銘柄がいろいろあって それも季節によって変わるから・・ 店頭でどれを選んでいいかわからないし
私は固有名詞を覚えるのが苦手だから(;'∀')
その時々の つまり時候や仕入れ状況と 私の気分に合わせた茶葉を選んでくれる店員さんに毎度感謝しております。
だから 何も考えずに入れておいしいのが 日本茶
いつも安定の味
あるいは期待を裏切らない「新鮮な喜び(刺激)」を約束してくれる日本茶
その点 紅茶とハーブティは 入れ方の工夫に手間がかかる
が まあ 変化を楽しむにはいいかな・・
しかも基本原料が輸入品だからなぁ・・。
しっかりとした味と香りのものが欲しければ
店内で品質を確かめる必要もある(それは得意ですw)
(はっきり言って 入荷したてのものを買って 自宅で保管するのが私流。
同じ店でも 入荷後時間がたてば それだけ質が落ちる(劣化と言いたいレベルで)のがハーブ。
なので 入荷直後のものを見定めて購入し、自宅で保管したほうが品質は保てる。
外見と ケースをあけたときの香りで
その店内にある品の品質は だいたいわかる。
店員の売り口上は巧みにスルー、信用しないw 自分の目と鼻で選ぶ)







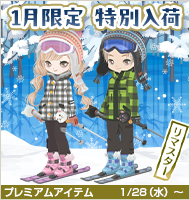


















その小売り店では ひっそりと商品の品質の良さを大衆に印象づけたり
地方から来た人間へのアピールや
若者を将来の顧客(生涯にわたって買いに来てくれる客)にすべく 客の様子を見定めながら客に 商品を見極めるための教育もやっていたように思う
そういう店舗面積は小さめでも 品種の奥行と品質の高い店が どんどん消えていったのが
平成であり、意図的に行政から追い立てられていったのが橋下以後の維新であった。糞!
イタリアに行ったとき 何気に ハーブ類を店頭で確かめたとき その鮮やかな香に驚いた。
しかも 価格が 日本での10分の1以下だった。
同様の経験は 中国やトルコの辺境でも経験している (この時は 実もの系だったが)
だからこそ 昔ながらの 原料直輸入店の入荷日にあわせて 小売り品を買うか
あるいは 旅行のついでに 好みのものを買ってきて自宅で保存するのが
イチバンいいと思う
20世紀末までの大阪は 天下の台所としての面目をまだまだ 保っていたと思う
ちょうと 富山でも 案外 輸入のスパイス類の良いものが 原料の形を保ったまま小売りされていたように(さすが 薬売りの起点となった地)もっとも 富山のあの店は アンテナショップだった気もするが
一般論としては 百貨店の店舗は論外だわ
原料が輸入され きれいなパッケージに入れられたり あるいは 透明ケースに入れ替えて店頭に並んでいる間に香も質(光は大敵なのかも)も劣化しているから
・そういう意味では きちんと焙煎された麦茶は がぶ飲み用に便利だわ
冷やしてもホットでもおいしい麦茶
(しかも 昔ながらの老舗の麦茶は 案外 家庭での長期保存に耐える 味と香りが落ちない。
スーパーの麦茶は論外で、あれは開封直後から味が衰え、あっといいうまに色だけ(やや変なにおいつき)の代物になりはてる・・)
でも さすがに4か月くらい飲み続ければあきるので、年を越せば ハーブティも含めたその他のお茶が欲しくなる。
なので 夏の初めに だいたい12月まで使う分を計算して
きちんとした麦茶をまとめて買うことにしている
(来年購入するときように から袋もきちんと保管しているw商品名や生産者をメモするより、空袋を保管したほうが確かだもんw必要な時に確かめやすいし。メモを探すのもめんどしw)
・ちなみに 茶葉や麦茶保存用のケースは サイズもそろえて完備してます 我が家は。
保管場所も確保(意外と場所取りw)
(予備のから容器も含めて)
最近は 袋の口をきっちり閉める小物も手軽に使えるから便利だわ