お裾分け、お福分け
- カテゴリ:日記
- 2025/02/09 21:43:32
「お福分け」という言葉があるということを、つい先日まで知らなかった。
今まで私の周囲には使う人がいなかったからだが、
わりと最近になって作られた言葉なのかと思って調べたら、
そうでもなくて、江戸時代からある言葉だった。
コトバンクで「裾分け」、「お裾分け」、「福分け」、「お福分け」を検索した。
意味は分かっているので、過去の文献に登場した例(できれば初出)を知りたい。
4つとも「精選版 日本国語大辞典」の説明が出てきた。
【裾分】
「さもあらばほうびの千両をすそわけいたそふずるにて候」
浮世草子・傾城色三味線(1701)
【御裾分】
「それもおすそわけはどうだの」
滑稽本・浮世風呂(1809‐13)
【福分】
「今世にも外よりくれたる物を分ちて人に贈るを福わけといふ」
随筆・嬉遊笑覧(1830)
【御福分】
「何れからの御進物かお福分けに一反づつ頂戴したい」
歌舞伎・裏表柳団画(柳沢騒動)(1875)
「裾分」は室町時代には使われていて、日葡辞書(1603‐04)にも登場する。
「裾分」という名詞が最初にあって、そこから「お裾分け」が出て、
やがて「福分け」が出て、「お福分け」が出たという順番のようだ。
朝日新聞の過去記事(ことばの広場)に書かれている説明によると、
室町時代には必ずしも上の人が下の人に与える物とは限らなかったが、
江戸後期の「譬喩尽」という本には「すそわけといふ詞は失礼なり」
と書かれていて、目上の人に使うのは失礼という考え方が定着している。
江戸時代の間に、そういう考え方が広がったのではないかと思われる。
あと、上に引用した使用例を見ていて、面白いと思うのは、
「お裾分け」と「お福分け」はもらう方が使っているということだ。
(つづく)





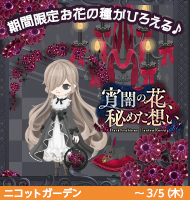














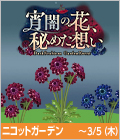







元々は目上の人に対して使うこともあったらしいのですが、
それは失礼じゃないかと考えるのも、たしかに自然な発想ですね。
つづきは今日の日記に。
だから、福分けという言葉ができたんでしょうね。
「はい。お裾分け~」って誰かにお渡しするのは、失礼なことになるんですね。気を付けないと(;''∀'')
日本文化らしい言葉の派生ですね。
鰻を背から開くか、腹から開くかでもちゃんと理由があって
そういうのを調べていくと
本当に日本人って細かい(?)ことにこだわる面白い人種だなぁと思います( ´艸`)