お裾分け、お福分け(続)
- カテゴリ:日記
- 2025/02/10 22:44:13
たぶんこうだったんじゃないか劇場
室町時代ころの話。
「殿から頂いた褒美の裾分けじゃ、受け取れ」
と言って、家臣が殿様からもらった褒美の一部を自分の配下の者に分け与えた。
あるいは、その頃は目下の者に渡すものと決まっていたわけではなく、
「○○殿からたくさん頂いたので、裾分けで失礼じゃが受け取って下され」
と言って、同輩や、場合によっては目上の相手に渡すこともあった。
すると、もらった方は「裾分け」に「お」をつけて丁寧にして、
「主から頂戴したお裾分けじゃ」、「○○からもらったお裾分けじゃ」
とか言って、それを家族に見せたりした。
こんな風にして「お裾分け」という言葉が広く使われるようになった。
それが江戸時代にもなると、何かをたくさん手に入れた仲間に対して、
「そんなにたくさんあるんだから、こっちにもお裾分けしてくれよ」
とか言って、おねだりに使ったりもするようにもなる。
一方、「裾分け」はいかにも端っこの余りものを目下に渡すようで、
失礼じゃないかと言い出す人たちが出てきて、
代わりに「福分け」、「お福分け」という言葉が使われ始める。
(さらに、つづく)




















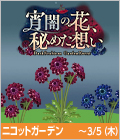








こんばんは。(しばらくさぼっていました)
江戸時代だと、町人の中にどう広がったかがポイントでしょうね。
発祥が江戸か京か大坂か、それによっても違いがありそうだし、
いろいろ調べると、まだ何か分かってくるかも…
誰かが「その言い方って、目上に対して失礼じゃないか?これからはお福分けって言うよ」と
言っても、それが広まるまでだいぶ時間が掛かったでしょうね。
誰が最初に言い始めたのかなぁ。
江戸時代だから…幕府の役人あたりでしょうか。中央の役人がそういう言葉を使い出すと、
すぐ広まりそうな気もします( ´艸`)