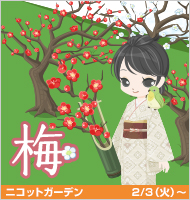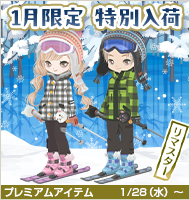☆防災の日☆
- カテゴリ:日記
- 2025/09/01 14:45:25
9月1日は「防災の日」です。
この日は、対象12年9月1日に発生した関東大震災、昭和34年9月に襲来した伊勢湾台風などをきっかけとして、昭和35年の閣議によって定められました。
また、昭和57年には、全国的な防災普及行事の展開のために防災週間を設置することが、それぞれ閣議によって定められました。
「防災の日」9月1に制定された最も大きな理由は1923年(大正12年)9月1日に発生した「関東大震災」という未曽有の大災害を教訓とするためです。地震による建物の倒壊だけでなく、その後に発生した大規模な火災や津波によって、10万人以上もの尊い命が失われたと言われています。この悲惨な出来事を風化させることなく、災害への備えの大切さを国民一人一人が再認識し、将来の災害に備える意識を高めることを目的として、「防災の日」は制定されました。災害はいつどこで起こるかわからないという意識を持つこと、そして日頃からの備えがいかに重要かを、私達に強く教えてくれています。
9月1日という日付には、もう一つ大切な意味が込められています。それは、日本が台風シーズンを迎える時期にあたるということです。昔から、立春から数えて210日目にあたる「二百十日(にひゃくとおか)」や220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、稲が開花し実を結ぶ大切な時期でありながら。台風が襲来しやすく、農作物に大きな被害が出やすい厄日として警戒されてきました。9月1日は、この二百十日に近い時期にあたることが多いのです。
実際に、過去の統計を見ても、9月は台風の上陸が最も多い月の一つです。そのため、「防災の日」は、地震や津波だけでなく、台風や大雨といった風水害への備えを改めて確認し、防災意識を高める機会としての意味合いも持っているのです。
このように、「防災の日」は、関東大震災という歴史的な大震災の教訓を未来に伝え、同時に台風シーズンへの警戒を促すという、二つの重要な意味合いを持って制定された、私達の命と暮らしを守るための大切な一日なのです。
『防災の日に実地したい対策』
家庭で実地すべき防災対策
自治体などが公開している「ハザードマップ」をチェックし、自宅周辺・通勤・通学先などの地域の災害リスクや避難場所、避難ルートを把握しておきましょう。地震・津波と、台風・洪水では災害の特徴が異なるため、安全に移動できる避難ルートが異なる場合もあります。避難場所への最短の道のりだけでなく、海、川のそばを通ることなく移動できるルート、そして地震・津波の場合は倒れやすい堀のそばなどを避けるルートなど、複数のルートを想定しておけると安心です。
9月1日は、年に4日ある「防災用品点検の日」(3月1日・6月1日・9月1日・12月1日)でもあります。家具の転倒防止策の点検や、高いところにあるものの落下防止状況の点検、懐中電灯やモバイルバッテリーといった防災に役立つ家電の点検、非常用に備蓄している品の点検なども忘れずに実地しておきましょう。期限の迫っている非常食などはこの機に家族で試食してみて、新たに補充する際の商品選びに活かすのもおすすめです。
企業で実地するべき防災対策
消防法で防災管理業務の実地が義務づけられているオフィスなどではもちろんのこと、対象外であっても、オフィスに備えられている消火器や火災報知器の使用期限が経過していないか、また従業員一人一人が消火器の正しい使い方や避難経路を知っているか、警報機が正常に稼働するかなどを改めて確認しておきましょう。定期的に防災訓練を行い、あわせて設備の点検を行うように決めておくと、従業員への防災教育にもなり、設備の点検漏れも防げます。また、消防法は随時改正されますから、現在の設備で最新の改正法に対応できているか、対応できていない場合は不足している事項なども確認し、防災対策を進めていきましょう。
『防災の日の取り組み』
防災の日には、全国でさまざまな防災訓練やイベントが行われます。イベントでは学校や地域、企業などが一体となり、防災意識の向上を図ります。具体的な取り組みとしては、以下のようなものがあります。
1.防災訓練
各地で避難訓練や救護訓練等が実地されます。これにより、実際の災害時にどのように行動すればよいかを学び、迅速かつ適切な対応ができるように備えます。
2.防災知識の普及
地域での防災講座やワークショップを通じて、地震や台風などの自然災害に対する知識を深めます。家族で防災計画を話し合い、緊急時の連絡方法や避難場所を確認することも大切です。
3.防災グッズを備えよう
防災の日に合わせて、家庭や職場で防災グッズの確認や補充を行いましょう。非常食や水、応急手当のキッド、ラジオ、懐中電灯などの備えが重要です。「もしも」の時に必要な防災グッズは、あらかじめ準備しておいて、定期的に点検しましょう。
4.防災リュックを備えよう
防災リュックは、災害発生時に最低限必要な日用品や食料品を詰めた非常用の持ち出し用リュックのことを指します。その主な目的は、突然の避難時に必要なものをすぐに持ち出せるようにすることです。また、避難所での生活に備えて、救援物資が届くまでの間、自立した生活を送るための必需品を確保することも重要な役割を担っています。日常的に中身を見直すことで大事な時に安心を担保してくれる重要なツールになります。9月1日は防災の日、この機に防災リュックの中身の確認や新規購入をご検討してみてはいかがでしょうか。
5.防災リュックの中身を用意するときのポイント
防災リュックの中身には最低限必要なものだけを入れましょう。水、非常食、懐中電灯、ラジオなど、避難時に必要なものがリュックの中身として基本となります。リュックの全体の重さは、男性で15㎏、女性で10㎏程度を目安にします。これは避難時にリュックを背負った状態で移動するためで、個人の体力に合わせて調整することが大切です。また、家族一人につき1つのリュックを用意し、子どもがいる場合は子ども用のリュックも準備するようにすることが重要です。
6.防災リュックの中身リスト
防災リュックの中身リストを紹介します。ぜひ参考にしてください。
(1)防災リュック本体
(2)携帯ラジオ
(3)LED懐中電灯
(4)非常食
(5)携帯浄水器または浄水タブレット
(6)防災ブランケット
(7)多機能ツール
(8)モバイルバッテリー・ポータブル電源
『防災の日をきっかけに、未来へ備えよう』
防災の日は過去の災害を振り返り、未来に備えるための重要な日です。自然災害はいつ発生するかわかりませんが、日頃からの備えと防災意識の向上が被害を最小限に抑える鍵となります。私達一人一人が防災の重要性を認識し、具体的な行動を取ることで、安全で安心な未来を築いていきましょう。防災の日を機に、家族や友人と防災について話し合い、共に備えを進めていきましょう。災害が発生した際には、冷静かつ迅速に行動し、自分や周りの人々の命を守るための準備を忘れずに行ってください。