64歳の機長解雇は 退職金をけちる為では?
- カテゴリ:日記
- 2025/09/06 18:01:24
JAL、飲酒機長解雇へ ホノルルで自主検査60回もゼロにならず
午後0時15分の時点で、0.05-0.07mg/Lのアルコールが自主検査で検知された。中部行きJL793便はパイロット2人が乗務する便で、通常は機長と副操縦士がペアを組むが、この日は当該機長と別の機長による、機長資格者2人体制を予定していた。当該機長はホテルを出る前に、同乗するもう一人の機長に体調不良を申し出た後、羽田空港にある運航本部に自主検査でアルコールを検知したことと、前日に飲酒したことを報告した。
JALでは、パイロットのアルコール検査を、自主検査も含めると4段階実施。当該機長が60回繰り返した自主検査は「自発的な検査」と呼ばれ、自身のアルコール耐性や体調を調べるもので、アルコール検査器を会社のシステムには接続せずに「オフライン」で実施する。その後、3回実施する検査は会社や国が定めたもので、システムに接続して「オンライン」で行う。1つ目が自宅やステイ先のホテルで行う「出社前検査」、2つ目が出発空港などに到着後、正式な検査前に実施する「事前検査」の2つが会社が定めたもの、最後に国交省の航空局(JCAB)が定めている「乗務前検査」を受け、アルコール度数がゼロであることを証明して乗務する。
当該機長は自主検査でアルコールが検知されたことから、出社前検査を行う前に会社へ報告したという。
当該機長が乗務予定だった28日の中部行きJL793便は、後続のホノルル28日午後4時35分発羽田行きJL71便(787-9、JA876J)のパイロットと交代して出発。JL793便は定刻より2時間8分遅れの28日午後4時28分に、乗客239人(幼児2人含む)と乗員12人(パイロット2人、客室乗務員10人)を乗せてホノルルを出発した。
一方、28日の羽田行きJL71便は、代わりのパイロットを日本から手配する必要があり、18時間41分遅れ、29日の羽田行きJL71便(787-9、JA875J)も、パイロット手配の影響が残り、18時間21分遅れの出発になった。
産業医が断酒通告
4日に会見した、安全問題の責任を負う「安全統括管理者」の中川由起夫常務執行役員は、「社会へのお約束を破ってしまった」と、南正樹・運航本部長、野田靖・常務執行役員総務本部長とともに陳謝。野田常務は「解雇も含めて処分を検討する」と述べた。
問題が起きた8月は、日航機墜落事故から40年の節目にあたる。中川常務は「ご遺族の皆様に申し訳ない」と謝罪した。南運航本部長によると、当該機長は当初からJALに入社したパイロットだったといい、事故当時の社内の状況を知る世代だった。中川常務によると、当該機長はアルコールに関する要注意者ではあったものの、飲酒リスクごとに3段階に分けた中では、もっとも低いリスクの要注意者に分類されていたという。
昨年2024年12月1日に起きた豪州のメルボルンで起きた飲酒問題後、JALはパイロットのステイ先での飲酒を、12月11日から社内規程で禁止。しかし、当該機長はステイ先で10回程度飲酒していたことがわかった。
8月初旬に身体検査を実施したところ再検査となり、下旬に行われた産業医との面談では断酒を指示された。この前日に、運航本部のアルコール対策専門部会分科会が開かれたが、健康管理を担当する部門との連携が不十分で、当該機長の情報は分科会の議題には上がっていなかった。
飲酒リスク基準見直し
中川常務は、要注意者の選定基準について「基準を見直す必要があると考えている。(当該機長を)リスクが一番低いと分類してしまったことを深く反省している」と述べた。要注意者全体の人数は「それほど多くないのではないか、という感触だ」と応じた
昨年12月にメルボルンで飲酒問題を起こした2人の機長(いずれも解雇済み)と比べ、当該機長は「普段の様子からは問題があるようには見えなかったため、過去の事例とは少し違う側面があると感じている」(中川常務)として、「日常的な行動だけでは見抜けない部分を、どうやって総合的に把握していくかが今後の課題だと認識している」と、会社側が行えるアルコール対策の課題を語った。
アルコール検知機の日付改ざんは「今回の事案で初めて把握した。会社側のシステムにデータが残るため、日付を変更しても意味はない」としつつ、「今後はより詳細なデータ活用を検討したい。検知器のデータだけでなく、勤怠や職場の面談状況など、さまざまな周辺情報も活用し、リスクを抱えた乗員(パイロット)に迅速なアプローチをしていきたい」(同)と、パイロットの心理状態の変化も含め、アルコール問題への対策に活用していく考えを示した。
メルボルン事案後の会社側が進めている飲酒問題の対策強化について、パイロット側の反応は「乗務前の検査を確実にやる、という意識は浸透してきている。しかし、今回の事案を防げなかったという点では『会社はもっとやるべきことがある』と思われているかもしれない。乗員の協力が不可欠であり、これからも理解を求めていきたい」と語った







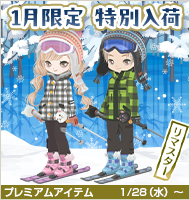


















一方、国際線の乗務から要注意者を外すといった対応については、「高リスクの乗員を国際線から一律に外すことのインパクトはまだ検討していないが、リスクの度合いに応じてメリハリをつけることも考えなければいけない」と、飲酒問題のリスク評価に応じた乗務を見直す可能性に言及した。
JALは新たな対策として、専門機関の支援や、1カ月以内の対策立案を目標としている。
◇
・産業医の診断を無視して 通常勤務を続けさせたうえで、一発解雇というのは、パイロットを管理する企業責任を放棄して、パイロット個人だけに責任を擦り付ける コスイ手口だ。
・そもそも64歳なのだから、減給のうえで数か月間の地上勤務に回して 定年退職させても問題がなかったはず
・しかも パイロット個人の飲酒問題と123便の墜落事故を絡めて語ることがおかしい
それをあえて記事にするということは、当時すでにパイロットとして乗務していた日航機機長が
40忌関連の記事 そして 123便の墜落時の生存者100名以上を国策として意図的に見殺しにした(もしかしたら自衛隊が生存者を焼き殺した)可能性もあるという調査結果をめぐって
心痛から 酒に手をだしてしまったという事柄を隠蔽するための姑息なJALのエグイ現実を暗示しているのか?なんて 憶測すら 呼び起こすのではないか??
・事実を隠蔽しようとすればするほど、年月がたつほどに 腐敗が広がる実例みたいな結果にならないように! 筋を通した処遇をしろ。
それは 形式だけを整えた処分ではなく、条理を尽くした対応をしろということ