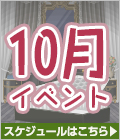メモ
- カテゴリ:日記
- 2025/09/27 07:55:48
【解説】南海トラフ地震の発生確率『60~90%程度以上』に見直し 80%程度からナゼ変わった? 専門家は「大きな地震が起きる可能性は少しずつですが高まっています」(MBSニュース) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a21ae500f5079df0f43e5f243df184a76d81f3f
9/26(金) 17:00配信
「今後30年以内の発生確率が「80%程度」とされてきた南海トラフ地震。政府の地震調査委員会は、その発生確率を「60%~90%程度以上」とする新たな発表」
「今回の大きな変更ポイントの1つは、室津港の隆起量データの見直しです。
新たな研究論文が発表されたことなどから、史料の記録や解釈を再検討し、隆起量データの不確実性を表す、つまり「データに幅を持たせる」ことに」・発生確率計算モデルの見直
「「時間予測モデル」ではひずみの蓄積は一定としていましたが、
・地震を起こすひずみの蓄積が一定ではなく、はらつきがある ・地震が起きた時のひずみの解放は、地震の規模によって異なる ・発生間隔は前の地震の規模に比例するがばらつきもあることを考慮した「すべり量依存BPTモデル」という新たな計算モデルを採用」「気をつけないといけないことは、今回の発表は、史料の解釈と計算方法の見直しによるもので、南海トラフの状況が変わったのではない」
取材と文:福本晋悟 MBS報道情報局 災害・気象デスク。おもに津波避難に関する課題をテーマに取材。人と防災未来センター特別研究調査員。神戸学院大学非常勤講師
◇ ◇
読みやすい記事だった。
これで 地震保険の掛け金が下がるといいのだけどなぁ・・
はっきり言って 今の料率では 地震保険に加入する意味がないといいうほど 掛け金は高く保証が低すぎる
あと、南海地震に関して言えば、伝え聞く1946年の時と同程度なら、耐震設計の今の家屋の建築密度によっては、かなり被害が軽くなるのではないかと言う気がする
むしろ 地区ごとの建造物の質と割合によって 地震被害の差がを大きく開くのではないかという気がするのですが・・。
隠れ断層の位置情報の全公開・周知徹底と建造物の規制を徹底し、隠れ断層の上には 建物をたてず、耐震・耐火住宅・建築物の比率を90%以上にできれば95%以上にしたり、地盤の質によあわせて建造物の密度を定めたり 建築時の防災設計の課題を設定することにより
直下型以外の地震被害はかなり防げる(人命にかかわらない程度に抑えられる)と思います。
せっかくの建築基準と建築技術水準を維持し より確かなものにすることによる 防災効果をもっと着目すべきではないかと考える
そして クルクル東海地震も何回(南海)トラフも オオカミ少年のようなたわごとは廃止すべき。
日ごろの備えは 個人の責任と 行政の責務、の両面から実効性を高めるべきと考えます。
ゆくゆくは 水被害にあいそうな場所、地震リスクの高い場所
など 地形・地盤・気象条件といった立地条件に合わせた 建築基準・許認可基準を定めることにより 自然災害により強い日本国に成長できると考えます。