ザ・果物 ~フルーツ王に俺はなる!~
- カテゴリ:日記
- 2025/10/14 00:36:40
今ではすっかり柑橘類売り場の常連になったグレープフルーツですが、70年代に輸入が自由化されたt当初、グレープフルーツ用のナイフとスプーンを購入して待ち構えた庶民の家庭では・・・
全然ブドウの味と違うじゃん!!
という声が漏れ、酸味と苦味を緩和スべく、砂糖をたっぷりかけて食べたことでしょう。その後、イスラエルで作られたスウィーティー種が入ってきて、現在の地位を獲得したとか。
これは、グレープフルーツの名の由来は「枝に実った様子がブドウの房のようだから」ということが、十分には説明されなかったための悲喜劇でした。
同様に、形の連想から名付けられたのが「パイナップル」。「パイン+アップル」であることはピコ太郎のおかげで(?)ご存知でしょうが、パインが英語で「松」の意味だとは知らない人もいるかも。
つまりパイナップルは「松の実」すなわち「松かさ・松ぼっくり」に形が似ていることからの命名なんですね。
Grokさんによれば、「15~16世紀、コロンブスが新大陸(カリブ海、1492年)でパイナップルを発見した際、ヨーロッパ人はその見た目が松ぼっくり(pinecone)に似ていると感じ」
たことに由来するそうです。
「スペイン語(「piña」、松ぼっくり)、フランス語(「ananas」、原住民語由来だが「piña」も使う)、ポルトガル語(「abacaxi」または「ananas」)など、ヨーロッパ言語では松ぼっくりを連想する名前と、南米原住民のグアラニー語の「naná」(優れた果物)に由来する名前が混在」していたそうですが、英語ではそれに加えて「果肉がリンゴのように甘酸っぱいことから「pineapple」と命名しました。当時、「apple」は具体的なリンゴだけでなく、果物全般を指す言葉として使われることがあり、松ぼっくりのような外見と果物らしい中身を表現したわけです。」とのことでした。ちなみに中国では「鳳梨」、さすがは「梨下に冠を正さず」の国?
さて、リンゴと言えば旧約聖書。アダムとイブが蛇の姿をしたサタンにそそのかされて食べた「禁断の木の実」。これはルネサンス期の宗教画ではリンゴが描かれ、「喉仏」を英語で「アダムズ・アップル」と喚ぶ起源にもなっています。
ところがこの木の実、「ヘブライ語の原典(創世記)では「木の実」(peri)としか書かれておらず、具体的な果物の種類は不明。ラテン語訳聖書(ヴルガータ、4世紀)でも「malum」(リンゴまたは果実一般)と訳され、曖昧さが残ります。しかし、ラテン語の「malum」は「悪(malus)」と語感が似ており、「罪の象徴」としてのリンゴに結びつきやすかった。」んですって。
なお、木の実を食べた二人が恥じらいを覚えて下腹部を隠したのは「イチジクの葉」、こちらは旧約聖書に明記していて、木の実もイチジクだった可能性があるようです。
そういえばギリシャ神話にもリンゴが登場してたな、と確認してみたら、トロイア戦争の原因となった「不和のリンゴ」とヘラクレスの伝説に登場する「ヘスペリデスの黄金のリンゴ」が有名なようで、どちらも原語では「mēlon」、本来は果物一般を指す言葉でしたが、ギリシャではリンゴが栽培され身近な果物であったことから「リンゴ」と結びついた、ということです。
「え、melon?」と思われた方。そうです、「メロン」もまた古代ギリシャ語では【果実全般」を指していたんだそうです。
それが「中世ヨーロッパで「melo」がウリ科の果実(現代のメロン、特にマスクメロンやスイカ)に特化し、英語「melon」、フランス語「melon」、スペイン語「melón」として定着。14世紀頃、ウリ科の甘い果実が中東からヨーロッパに広まり、「mēlon」の名が特定の果物に絞られた」んだそうです。
つまり、アップルもメロンも、その時代・土地での果物の代表、「ザ・果物」ということだったんですね。
まあ、秋は果物が美味しいからって食べすぎないようにしましょうね。





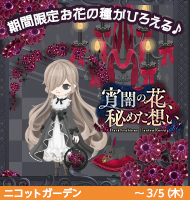














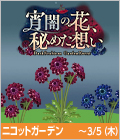





両親は食ってましたw
私は苦手~
グレープフルーツは、身がなっている状態が、ブドウみたいなんです。
初めて、見た時、びっくりしました。
「デカいブドウじゃん!」って思ったもの!
パイナップルも、松のリンゴだもんね(^^♪
ありがとうございます。懐かしかったなあ♪