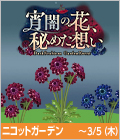維新の議員削減「比例復活」対象か
- カテゴリ:ニュース
- 2025/10/18 00:28:37
【高市自民】ネット騒然「要らない」「廃止して」吉村代表、国会議員大幅削減「比例復活」を標的→イヤなら連立拒否! カズレーザーが回答引き出した「カズ見事」「賛成!」「いらねー」 (デイリースポーツ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f12aa94517acdbf5d63b34705fb76946856ad664
小選挙区の比例復活制度をめぐる論点整理
小選挙区で落選した候補者が比例代表で復活する「比例復活制度」を廃止すれば、比例復活議員の割合が多い政党(立憲、維新、国民)ほど大きな影響を受けることになります。結果として、小選挙区で勝てる政党とそうでない政党との間で、議席数に大きな差が生じるでしょう。
小選挙区の落選票が完全に無駄になるため、死票が増えるという懸念もあります。
このような制度変更が行われれば、小選挙区で勝てない候補者は比例区に回るか、野党間で候補者を一本化するなどの選挙戦略が求められます。しかし、「反自民」などのスローガンだけで基本政策の異なる政党が候補者を一本化する場合、有権者から「政策を無視した野合」と見なされるリスクが高まります。
地方自治体の首長選挙では、外交、安全保障、エネルギー政策の異なる政党が同じ候補者を推薦することもありますが、それは、それらの政策に関係のない自治体の選挙だから出来ることであり、国政選挙ではそうは行きません。
私見:比例復活は容認すべき、比例単独候補の削減を
私個人としては、小選挙区で落選した候補者の比例復活は容認しつつ、比例区単独候補者の削減を検討すべきだと考えます。その根拠は以下の通りです。
1. 小選挙区落選候補者(比例復活者)の正統性
比例復活には、一定の民主的正統性が認められます。
・有権者への直接的な訴え: 小選挙区候補者は、選挙区内に選挙事務所を構え、街頭演説や討論を通じて政策を有権者に訴えています。これは、国民に対する説明責任を果たす行為であり、議員としての基本的な資質を示すものです。
・一定の支持獲得: 比例復活には、小選挙区で有効投票の10%以上を得る必要があります。これは、候補者が一定の民意を得ていることの証左です。
・惜敗率の反映: 当選者に僅差で敗れた候補者ほど、その地域の民意を強く反映していると考えられます。比例復活は、こうした「惜敗者」を救済する合理的な仕組みです。
2. 比例区単独候補者の正統性の問題点
一方で、比例区単独候補者には以下のような課題があります。
・活動の実態不足: 比例単独候補者は、選挙区で選挙活動をせず、政党の得票力だけで当選します。そのため、「顔の見えない議員」「選挙活動による審査を経ていない」といった批判が生じます。
・公認権力の集中: 比例名簿の順位は、党執行部の意向で決まることが多く、論功行賞的な運用がなされる場合もあります。これにより、議員の正統性が有権者ではなく政党に依存する構造が生まれます。
結論:比例復活制度をめぐる対立の本質
「比例復活は認めるが、比例区単独候補者は削減すべき」という立場は、「議員は地域の有権者と直接向き合い、選挙を経て選出されるべき」という民主主義の根幹に基づく考え方です。
一方で、比例復活制度そのものを否定する立場からは、以下のような批判が挙げられます。
・敗者復活への異論: 小選挙区で落選した以上、その地域の有権者の意思は「不支持」であり、比例で復活させるべきではないという考え方です。
・二重の救済: 小選挙区と比例代表という二つの制度で「二度チャンスを与える」ことは、議員の地位にふさわしくないとの批判です。
今後の制度設計に向けて
議員数を削減しつつ、議員の正統性を確保するためには、以下のような制度改革が議論の対象となるべきでしょう。
・比例復活を維持し、比例の単独候補の削減 (立候補者は選挙活動するべき)
・比例復活をなくし、小選挙区を増加+比例の定数削減 (一票の格差是正も)
・現在の小選挙区比例代表並立制をやめ、中選挙区制の導入 (昔に戻る?)
これらの改革は、選挙制度の公平性と民主的正統性のバランスを再考する上で、重要な論点となります。
維新は一つの選挙区から複数の当選人を選出する中選挙区制の導入も含めて検討しており、比例復活制度の廃止とセットで議論されています。ただし、中選挙区制は金権・派閥政治などの問題から、1994年の選挙制度改革で一度廃止された制度です。その復活には慎重な検討が必要です。