認知戦
- カテゴリ:日記
- 2025/11/23 12:03:40
近年、世界では武力を用いる事無く、他国の社会や政策判断を揺さぶろうとす手法が拡大しています。これは、ニュース、SNS、動画、さらには生成AIを利用し、標的となる社会に誤解や不信、分断を生じさせる行為です。
こうした動きを総称して「認知戦」と呼んでいます。認知戦の目的は、国民の判断を鈍らせ、社会の安定を揺るがし、国家の意志決定基盤を弱体化させる点にあります。
日本でも、災害時に突然拡散するデマや、選挙期間中に出回る根拠の乏しい噂、悪ふざけに由来する情報が発信が多くあります。
こうした「感情の高ぶりに乗じた情報拡散の構造」そのものが、外国勢力による認知戦で悪用され得る脆弱性です。
防衛省や外務省の資料で、外国勢力が偽情報の流布や世論操作を通じて他国の政策決定や社会の安定に影響を与えようとしている事例が国際的に確認されています。日本も同様の脅威環境の中に位置していることが明示されています。
重要なのは、国内発の自然な誤情報と、意図的な外部工作が同じ情報空間の上で重なりうる構造そのものを、安全保障上の課題として認識しておくことです。
SNSのアルゴリズムは、利用者の反応が多い投稿を優先的に表示する仕組みを持ちます。怒り、不安、驚きといった強い感情を喚起する情報は反応が集まりやすく、
その結果、感情を刺激する投稿が短時間で大量に拡散しやすい構造が形成されています。
国外勢力がこれを悪用する場合には、意図的に感情を揺さぶる情報を投入し、アルゴリズムの自動拡散機能を利用して標的社会に影響を与えることが可能となっています。これが現代の認知戦が可視化しにくいにもかかわらず強力である理由です。
生成AIは、文章、画像、動画、音声といった多様なコンテンツを、数秒から数十秒という短時間で生成できる技術です。
特に、本人の声に酷似した音声や、実在の写真と区別が付きにくい画像、あるいは実際に起きたかのように見える映像表現など、従来であれば専門的なスキルと時間を要した偽情報を容易に作成できる点に特徴があります。
生成AIが作り出す文章は、SNS上の自然な言い回しや流行語を学習しているため、一般利用者にとって真偽の判断が難しくなっています。
この構造が、現代の認知戦を過去とは比較にならないほど強力かつ可視化しにくいものへと変質させている要因です。
攻撃者は、偽情報を自ら拡散する必要はなく、AIで生成した情報を「アルゴリズムに乗せる」だけで、情報空間全体に影響を及ぼすことが可能です。
認知戦は、外形的には通常のニュースやSNS上の投稿と区別がつきにくいため、
その進行は日常の中で自覚しにくく、その効果は国家の安全と社会の結束に深く浸透します。
日本では安定を保つために、防衛省を中心として三つの中核政策を掲げています。
これらは国家安全保障戦略(NSS)、国家防衛戦略(NDS)、防衛力整備計画(DFP)という「戦略3文書」に正式に明記された政策で、憶測や推測ではなく、一時資料に基づく国家方針です。
①情報機能の強化(NSS:国家安全保障戦略)
国家安全保障戦略は、外国勢力による偽情報の流布や認知領域を狙った攻撃に対し、政府全体として情報収集・分析体制を強化する方針を示しています。
多様な情報源からのデータを統合的に扱い、認知領域への攻撃を早期に検知し対処する能力の向上が求められています。また内閣官房、防衛省、外務省など関係機関の連携体制を新た構築する事が明記されています。
②偽情報の真偽・意図を見極め無力化する。(NDS:国家防衛戦略)
国家防衛戦略は、認知戦への本格的な対処能力を2027年度までに整備する事を明確に規定しています。具体的には、偽情報の真偽判定を行う分析体制の強化、
自衛隊・防衛省の情報機能の抜本的拡充、そして日米同盟や同志国との情報共有・共同対処の深化が含まれます。これにより国外勢力による情報操作の影響を最小化し、国家の意志決定の自由度を確保することが目的です。
③AIによる自動検知と迅速な発信体制(DFP:防衛力整備計画)
防衛力整備計画は、AIを活用してSNSや公開情報を自動収集・分析し、偽情報の検知・真偽判定を迅速化する方針を示す。特に、情報拡散の経路や影響範囲を分析する機能を強化し、適切な情報を迅速かつ戦略的に発信する体制を構築することが求められている。これにより、偽情報が社会に与える影響を最小限に押さえることが可能となります。
防衛省は「日本は偽情報の流布・世論調査・謀略といった行為を一切実施しない」と宣言(防衛省「認知領域を含む情報戦に関する考え方」)。
これは、日本が国際社会において攻勢的情報戦を行わないという基本姿勢を示すものです。一方で、同じ文脈の中で政府は「外国による偽情報の流布や認知戦の脅威には断固として対応する」と言う立場を明確にしています。日本は攻撃のための情報戦は行わないが、「守る為の情報防護」重要であり、その体制整備を急速に進めているという点が国家戦略上の本旨です。
認知戦は、攻撃者が偽情報や感情を刺激する内容を投入し、アルゴリズムを利用して社会の不信や対立を増幅させる手法であります。
この攻撃は外形的な兆候が乏しく、多くの場合「自然な投稿」や「もっともらしいニュース」として私たちの目の前に現れるため、個々が気づきにくい特徴を持ちま
す。
第一に、強い感情を喚起する投稿ほど慎重に扱う姿勢を持つ。
怒り、恐怖、不安を刺激する情報はSNSの構造上、意図の有無を問わず拡散しやすい。攻撃者はこの特性を利用し、社会の感情を揺さぶろうとします。
したがって、感情を大きく動かす情報が現れた際には、「なぜ今この情報が出てきたのか」「だれが特をするのか」といった視点を持ち、即座の共有を避けることが認知戦の入り口を封じる第一歩になります。
第二に、画像・音声・動画であっても、生成AIによる作成の可能性を念頭に置く。
現代のAI技術は、本物と区別がつきにくい偽映像や合成音声を短時間で大量に作成できる。情報の形式が「映像・音声であれば信頼できる」と言う前提は生成AIの普及によって既に成り立たなくなっています。
第三に、出所が不明な情報や、急速に拡散している内容には距離を置く姿勢をる。
外部勢力による情報工作が最も効果を発揮するのは、情報の真偽ではなく、「拡散の速度」が社会の思考を上回る瞬間です。拡散の波に一呼吸おいて向き合う姿勢は、社会全体の冷静さを支えます。
これらの行動は、認知戦に引っかからないための基礎防御です。そして、この慎重な判断こそが、攻撃者に対して「日本社会は揺さぶりにくい」というメッセージを送り、結果として、外部勢力の認知戦の効果を著しく低下させる「強靱性による抑止)」を形成します。
攻撃者は、揺さぶりが効かない相手には、攻撃の費用対効果を見失い、行為をためらいます。国家の制度的対処と国民の判断力が両輪となり、外部からの認知戦を抑止する基盤となるのです。
SNSとAIの時代において、日本の安全を守る力は、国の防衛体制だけではなく、日常の情報に冷静に向き合う国民の姿勢によって支えられています。
こうした姿勢が積み重なることで、日本は認知戦に動じない社会的強靱性を獲得し、それが日本の土台の弱体化を防ぎ情報空間の自由度を守る抑止力の一部を構成する力となります。




















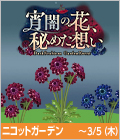








かわゆすぎ^^
とっても似合ってます。
金髪めずいね^^
こういうのってある意味怖いです。
政治の世界でもSNSです。普通に呟いたものが大きくなります。
ほんまあほか?って言うような事でも乗せます。
私的にはそんなんに頼らんと会談を増やしていっぱい話したらええねん。
そしたら相手の奥まで見れるかもしれんwwww
AIの文章に頼らんと自分の思ってる事言うたらええねん。
今の高市さんは、おっさん議員の言う事を聞き流す器量ではないと思います。
思いのままに動かされてるだけです。
認知症のお年寄りの数を増やして
国の機能を麻痺させることでつ ( `・ω・´ )b
・・・うそでつ ( ´・ω・` )