節々の痛みゼロを目指す日
- カテゴリ:占い
- 2025/01/30 15:45:22
ニコットおみくじ(2025-01-30の運勢)

こんにちは!冬型の気圧配置が続く。
九州から関東の太平洋側は広く晴れる。
北陸や東北、北海道は雪で、日本海側では吹雪く所も。
沖縄は晴れ。
【節々の痛みゼロを目指す日】 Aiming for a Pain‐Free Day
☆節々の痛みゼロを目指す日は東京都江戸川区にある、
あしすと訪問リハビリ鍼灸マッサージ院さんが提唱した記念日です。
この日は高齢者をはじめとする、
節々の痛みに苦しむ人々への理解と支援を深めることを目的としています。
日付は「いた(1)み(3)ゼロ(0)」の語呂合わせから選ばれ、
「痛みゼロ」を目指す願いが込められています。
2022年には一般社団法人日本記念日協会さんにより、
正式に認定されました。
この記念日は自宅で過ごす人々に対しても、
質の高いリハビリサービスが提供されるべきだという理念のもと、
設けられました。
[あしすと訪問リハビリ鍼灸マッサージ院]さん
住所(本院):東京都江戸川区下篠崎町9-2 ソレイユ2階
お問い合わせ:03-3698-0211
診療時間 :月~金・土・祝
*土曜日に限り17:00までとなります
〔江戸川区でリハビリ・マッサージをご検討の皆様
寝たきり・歩いての通院が困難な方がお近くにいる方〕
・元気になりたいけど痛くて病院に行けない
・個人で気軽に自分に合ったリハビリを続けたい
・自分の力で生活出来るようになりたい
・元気になって近所の人とコミュニティを広げたい
・職場復帰を目指してリハビリがしたい
・マッサージでリフレッシュしたい
・あきらめていた趣味を再開して充実した生活を取り戻したい
≪このような方々にご利用いただいております≫
・車椅子を利用されている方
・多くの時間を布団やベッド上で生活されている方
・自力で外出や歩行が困難な方、食事介助が必要な方
・要介護2以上の方
(要支援や要介護1もご利用実績があります)
●要介護度
@「要介護」「要支援」「自立」の3つを基準に分けられる
介護保険を利用するには、
必ず「要介護認定」を受けなければいけません。
そして・・・
「要介護認定」により、
利用者の心身状態や生活環境を確認しまして、
その人がどの要介護度に当たるのかを決定します。
要介護度とは、
どの程度の介護を必要としているかという度合いを重い順に、
「要介護」「要支援」「非該当」の3段階に分け、
さらにそれら3つを「要介護1~5」、「要支援1・2」、
「非該当」の8段階の区分で表したものです。
☆要介護度の状態区分
大区分 小区分 適合する人
要介護 1~5 日常的に介助が必要な人
要支援 1と2 介助が必要だが、
比較的自立した生活が出来る人
非該当(自立) 介助の必要が無い人
要介護度とは、
介護保険の利用者がどのくらい介護を必要としているかを、
判断する基準として用いられます。
したがいまして、介護保険サービスを利用する為には、
予め「要介護認定」を受ける必要があります。
まだ申請をしていない人は手続きを進めてください。
★要介護認定から介護保険利用
まず始めにすべきことですが「介護保険の申請」です。
□介護保険の申請
役場の担当窓口で行います。
それから「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定とは・・・
「本当に介護保険を必要とする状態か、
要介護度のレベルはどれくらいか」を、
審査・判定してもらう手続きのことです。
要介護認定の申請は、市区町村の役所や役場、
又は地域包括支援センターさんの担当窓口で受け付けています。
■介護保険
国で定められた法律で・・・
「年齢が40歳以上のすべての人が加入し、
介護保険料を支払うこと」
このように義務づけられています。
主な対象者は、65歳以上の「第1号被保険者」の方で、
第2号被保険者は40~64歳の方です。
「第2号被保険者」の人でも、
「特定疾患」として定められた16病名が原因で、
介護やサポートが必要になった場合です。
若くして脳梗塞や脳出血、くも膜下出血により後遺症が残ったり、
認知症(若年性アルツハイマー病)等で、
日常的なサポートが必要になったりした場合は対象となります。
◇要介護認定を申請する為の、申請時に必要な書類
▲介護保険翔または健康保険証
「第1号被保険者(65歳以上)は介護保険証、
「第2被保険者(40~64歳)は、
医療用の「健康保険証」を提出する。
第2号被保険者は要介護認定を受けてから、
介護保険証が発行される。
△申請書(要支援・要介護認定申請書など)
氏名、生年月日、住所、電話番号の他、
被保険者番号や主治医や医療機関の情報も記入します。
申請書は市区町村の担当窓口や、
地域包括センターの窓口で入手します。
ホームページなどからダウンロードできる場合もあります。
▲印かん
必ずではありませんが地域によっては、
認め印が必要な場合があります。
*介護保険証を失くしてしまった場合は、
市区町村の担当部署で再交付が受けられます
問題 上記、要介護認定の申請が受理されますと、
次は「認定調査(訪問調査)」を受けることになります。
又、認定調査と同時に必要となるのが「主治医の意見書」です。
「認定調査」と「医師の意見書」をもとに、
介護サービスの必要度を審査します。
そして、要介護認定の審査は一次判定(コンピュータ―が審査)と
二次判定(介護認定審査会)さんが審査します。
全ての審査が終わり、介護認定審査会さんの審査のもとに、
市区町村が要介護認定を行います。
要介護認定では「要介護度」の介護状態のレベルを決定し、
最終的に「要介護度」が明記された「〇〇通知書」が、
申請者の自宅に郵送されます。
〇〇に入る言葉を教えてください。
1、合格
2、自己
3、認定
ヒント・・・〇〇〇
公の機関が、
資格や事実の有無や物事の程度等を調べて決めることです。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。



















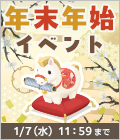










感謝ばかりです。
そうでしたか、お母様がでしたか。
審査が通るのに、随分かかりましたか。
そうですか、大阪は他県より厳しいのですか。
貴重なご意見をありがとうございます。
この先ですが、色々と諸事情があるはずですが、
なるべく審査が簡易で、なお且つ、早くなるとよろしいですね。
重複しますが、本日は4回もコメントをありがとうございました。
随分かかりました。
大阪は他県より厳しいみたいです。
コメントとお答えをありがとうございます。
かげねこちゃん、お疲れ様です。
はい、調べないでですね。
了解です。
おおお~、素晴らしいですね!
問題の答えは3番の認定です。
凄いですね、大正解です!!
やりましたね!やった!やった!
どうもおめでとうございました(祝)
今回は調べないで答えますね。
3.認定
ではないでしょうか?(間違ってたらごめんなさい)