モズク
- カテゴリ:占い
- 2025/04/17 15:45:09
ニコットおみくじ(2025-04-17の運勢)

こんにちは!高気圧に覆われ、全国的に晴れる。
沖縄は曇りのち雨。
気温は各地で平年より高く、東日本や西日本では夏日になる所も。
【モズク】 水雲 Nemacystus decipiens
mozuku
Stringy seaweed
☆シオミドロ目ナガマツモ科に属する褐藻(かっそう)の一種です。
<概要>
〇モズク
国内での産業的規模の養殖は沖縄県だけが成功しています。
@モズクについて
「もずく」は古くから全国各地で食用にされてきた海藻の仲間であり、
沖縄地方では昔よりもずくを三杯酢(さんばいず)で食されていた為、
酢のり=「スヌイ」とも呼ばれています。
★三杯酢
三杯酢に必要な調味料は、酢、味醂(みりん)、醤油の3つです。
□基本の割合
三杯酢の割合は、酢、味醂、醤油を同じ量だけ混ぜ合わせます。
3つの調味料をスプーン1杯ずつ、
合計3杯混ぜた点から三杯酢と呼ばれています。
混ぜる前に味醂を耐熱容器に入れまして、
電子レンジ600Wで1分加熱しますと、アルコールを飛ばせます。
アルコールが苦手な方や子供でも安心して使用出来ます。
多く作り過ぎた場合は、冷蔵保存で約5日保存が可能です。
■二杯酢との違い
◇二杯酢
酢と醤油、それぞれ同じ量を混ぜたものです。
混ぜ合わせてから鍋で煮立たせまして、冷ましたら出来上がりです。
1カップ(200CC)ずつ合わせて、多めに作っておくと便利です。
三杯酢との違いは、味醂が入らないことです。
甘さが少ない分、サッパリとした味に仕上がります。
酸味を効かせた和食の和え物だけではなく、
餃子や春巻きのタレ、魚介のマリネやハムサラダのような、
油っぽさや生臭さを抑えたい料理に向いています。
■三杯酢の特徴
◇甘味があってまろやか
三杯酢の特徴は味醂の甘味がありまして、酢の酸味を抑えられる点です。
その為、酢のツンとした鼻につく臭いが苦手な方、
酸味が苦手な子供にも使用しやすい酢です。
▲どうしても酸味が苦手な場合の対処法
・小さじ2杯程の出汁汁を加える
・酢も加熱して酸味を飛ばす
・癖が無く、スッキリとした味わいの穀物酢や米酢を使用する
◇和食にも洋食にも対応出来る
三杯酢は色々なおかずに対応出来ます。
野菜や海藻類等の癖が少ない食材から、
魚介類等の幅広い食材に使用出来ます。
そして、油を加えますとアレンジもしやすくなります。
▲代表的な料理
・和食:モズク酢、なます、酢の物、心太(ところてん)のタレ
・洋食:サラダのドレッシング、南蛮漬け
・春雨のサラダ
◇三杯酢を使用したアレンジレシピ
・モズクの酢の物 ・キュウリの酢の物
・紅白なます ・春雨サラダ
★モズク類の種類
モズク類は多くの種類がありまして、
その中で主に食用とされているのは6種類で、
国産で産業的規模の養殖は沖縄だけが成功しました。
□日本産のモズク類
・ニセモズク ・キタニセモズク
・キシュウモズク ・オキナワモズク
・タジマモズク ・ニセフトモズク
・フトモズク ・マギレフトモズク
・サンリクモズク ・サントウフトモズク(新称)
・クロモ ・ニセクロモ
・キタクロモ ・フサクロモ
・モズク ・ニセクロモズク
・クロモズク ・フサモズク
・クサモズク ・イシモズク
これら20種類くらいが含まれています。
■オキナワモズク属、イシモズク属、クロモ属
2007年に2つ目の種として、キシュウモズクが記載されました。
この種は東北以南に分布しまして、
オキナワモズクよりかなり長い同化系を持つことが特徴ですが、
その外観や食感はフトモズクとオキナワモズクの中間位で、
新種として認識される以前も「フトモズク」として、
食用にされてきました。
実際、神戸市にあるスーパーで四国産の「フトモズク」として、
販売されていたものは「キシュウモズク」であったことから、
かなり広く流通しているようです。
又、既に試験的な養殖も行われていることから、
今後さらに一般的な食品になる可能性があります。
独特のぬめりと柔らかさを持ったこの黒っぽい褐色の色のモズクは、
数ある海藻の中でもひと際、美味と称されています。
@養殖されている種類
・オキナワモズク(フトモズク)
・モズク(イトモズク又はホソモズク)
これら2種類があります。
その中のほとんどが「オキナワモズク」で形態は粘着に富みまして、
太さ1、5~3、5mmの褐色から黒褐色の枝が、
不規則に分岐した琉球列島特産種で、全国一の生産量を誇っています。
☆オキナワモズク
ナガマツモ科の海藻で、南は八重山諸島から北は奄美諸島に分布しまして、
食感が良く、コシがあり、色々な料理の食材に最適です。
@名前の由来
「モズク」の名前は、
他の海藻にくっ付いて育つという「藻付く」から由来しています。
★本土のモズク
ホンダワラ等の海藻の枝に生えています。
□ホンダワラ 馬尾藻 神馬藻 穂俵 Sargassum fulvellum
(Turnner)C.Agardh
Sargassum fulvellum
褐藻鋼ホンダワラ科ホンダワラ属の海藻の一種です。
同じホンダワラ科には、ヒジキやアカモクが挙げられます。
■沖縄のモズク
海中でゆっくり揺らぐような動きから、
「水雲」「海雲」とも表現されたりもします。
沖縄では昔から三杯酢として食されていることから、
方言で酢のりという意味から「スヌイ」「スヌール」「スヌル」、
宮古島では「ススズイ」と呼び方も様々です。
@養殖の歴史
古くより食されてきました「モズク」を、
昭和50年から養殖手法の実証実験を行いまして、
恩納村(おんなそん)漁業研究グループさんと、
水産業改良普及所さんの共同研究によりまして、
初めて養殖モズクは昭和52年に水揚げされました。
その後、色々な改良や試験を繰り返し、現在の養殖技術が確立されました。
問題 沖縄県内でモズク生産量が日本一の市名を教えてください。
1、うるま市
2、豊見城(とみぐすく)市
3、宜野湾(ぎのわん)市
ヒント・・・〇沖縄県内でモズク生産量が多い地域
2020年の沖縄県内の生産量は、約2万2千トンです。
@モズク生産量日本一の市 約6000~8000トン
☆市名の由来
沖縄の方言で「珊瑚の島」のことを、
「正解の市名〇〇〇(〇〇=珊瑚、〇=島」と呼びます。
お分かりの方は数字もしくは、
沖縄県内でモズク生産量が日本一の市名をよろしくお願いします。





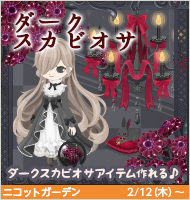

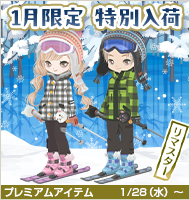












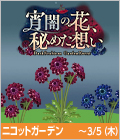






スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、掲載したように沢山のモズクがありますね。
私は全てのモズクを食したことがありません。
そうですね、いわれてみますと、夏場にお世話になることが多いですね。
今年も暑い予報がされていますので、サッパリと頂きたいものですよね。
夏場にお世話になる食材のイメージです。
イベント開始後で多忙のなか、コメントとお答えをありがとうございます。
そうですか、調べてくださりましたか。
恐れ入ります。
おおお~、1番のうるま市ですか。
問題の答えは、その1番のうるま市です。
凄いですね!やりましたね!
かげねこちゃん、大正解です!!
どうもおめでとうございました(祝)
今回も調べました。
1、うるま市
ですね。