県民ふるさとの日(富山県)
- カテゴリ:レジャー/旅行
- 2025/05/09 00:49:30
こんばんは!9日(金)は、
西日本では西から雨の範囲が広がり、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。
東日本は夕方以降に雨の降る所が多くなりそうです。
北日本は午後、次第に雲が多くなる見込みです。
南西諸島は雲が多く、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。
【県民ふるさとの日(富山県)】
☆「県民ふるさとの日」は、1883年(明治16年)5月9日に、
富山県が設置されてから130年の節目の2013年に誕生しました。
<概要>
〇県民ふるさとの日(富山県)
富山県民にとり、ふるさとの日はただの記念日ではありません。
それは、過去と現在、そして未来への架け橋となる大切な日です。
@県民ふるさとの日の起源
★置県(ちけん)130年の節目
2013年(平成25年)、富山県は置県130年を記念して、
「県民ふるさとの日」を制定しました。
これは富山県が一度消滅した後、
1883年(明治16年)に越中国から分離し、
再び独立した県として設置された日を祝うものです。
□富山の歴史
かつて能登国が属していたこともある越中国です。
江戸時代には富山藩領と加賀藩領が共存し、
明治の廃藩置県では一部が金沢健となり、
残りは富山県となる等、複雑な歴史を巡ってきました。
◆旧石器時代の出土品
旧石器時代の出土品が富山県で確認されている為、
この時代から人類は富山の地で暮らしていたと考えられています。
3世紀末から4世紀に大和政権が誕生し、
列島支配が強化し始めた頃、北陸一帯は越と呼ばれ、
7世紀には大和政権の支配下にありました。
*越(こし)・・・「古志」や「高志」とも書かれています
律令国家が成立した7世紀後半に・・・
・越前
・越中
・越後
これら3国に分かれたと推定されています。
越中となったのは・・・
・射水(いみず) ・砺波(となみ)
・婦負(ねい) ・新川(にいかわ)
これらの4郡です。
後に約15年間、能登国が越中国に属する時期はありますが、
4郡から成る越中国は既に現在の富山県とほぼ同じ領域でした。
国府射水郡(現:高岡市伏木)に置かれ、
ここに越中守(えっちゅうのかみ)となりましたのは、
大伴家持(おおとものやかもち)さんです。
◇佐々成政(さっさなりまさ)公によって統一された中世の越中
中世の越中は倶利伽羅(くりから)峠の戦いや一向一揆が起こる等、
激しい争いが繰り返されながら、戦国時代を迎えます。
天正11年(1583年)に越中は佐々成正公により統一されますが、
佐々成正公は前田利家公が先導を務める、
豊臣秀吉公の大軍に討伐されます。
この結果・・・
越中4郡のうち、婦負と射水、砺波の3郡が、
加賀藩前田家の領地になります。
後に新川もここに加えられました。
◆前田利次(まえだとしつぐ)公が初代藩主の富山藩が誕生
加賀藩の所領はこの時加賀と越中、
能登を合わせて百万石どころか120万石ともなっていた為、
幕府に厳しく監視されていました。
その警戒を緩める為、婦負と新川の一部を富山藩として誕生させ、
前田利次公が初代藩主となりました。
◇富山県誕生までの変遷
明治4年(1871年)の廃藩置県により・・・
・旧富山藩領 → 富山県
・旧加賀藩領 → 金沢健の一部
このようになります。
しかし、富山県の正式な成立は明治16年(1883年)で、
それまでの12年間、富山県は極めてややこしい変遷を巡ってきました。
▲富山県が成立するも新川県に統合
廃藩置県で富山県が成立したと思いきや、すぐに富山県は廃されまして、
砺波と婦負、新川の3郡が新川県として新設されます。
これは小規模な行政区画が分散、錯綜(さくそう)しまして、
分布した地域が全国で散見(さんけん)された為、
行政区域として纏(まと)まりを欠いた状態を目的によるものです。
射水郡はこの時同じく新設された七尾県に属しますが、
七尾県も廃止されたことで新川県に後から移されまして、
越中全域が新川県になります。
△富山県は石川県から独立
明治9年(1876年)の府県統合で、
新川県も廃されまして、石川県に編入されます。
このように近接した県同士の大規模な統合は、
北陸だけの事例ではなく、全国的な動きではありましたが、
その背景にありましたのは、明治政府の経済政策です。
府県は現在のように自治体ではなく、国家の下部機関であった為、
政府は附件合併によりまして、
地方経営にかかる費用を合理化しようとします。
しかし、この頃の石川県議会では、
越中の議員団の主張は少数派として、退けられる傾向にありました。
治水対策を求める富山出身の議員に対しまして、
加賀・能登出身の議員は道路整備を主張した為に、
路線の対立が生まれ、越中では分県運動が盛り上がりまして、
明治16年(1883年)に、ついに分県します。
そして・・・
富山県が正式に誕生しました。
◆現在は呉東(ごとう)と呉西(ごせい)からなる
現在の富山県は大きく呉東と呉西に分けられています。
△呉東
富山地域と新川地域に分けられています。
▲呉西
高岡地域と射水地域、砺波地域に区分されています。
このように、それぞれ越中4郡がベースになっています。
藩政初期までは呉羽山(くれはやま)よりも、
神通川(じんつうがわ)で越中を二分する考えがありました。
明治20年頃の史料においてもまだ呉東と呉西の概念は見られず、
この考え方がようやく登場したと考えられるのは、
明治末期から大正初期です。
さらに、昭和初期になりますと、
地誌において呉羽山が東と西で平野を二分するといった表記が見られ、
呉羽山の緩やかな起伏が平野を分割境界という認識が広がりました。
問題 呉東と呉西の文化や言語的な違いが、
富山県民に浸透していることを考えますと、
呉羽山がただの地理的シンボルであったというだけは疑問符です。
次の文章の???の中の人物名を教えてください。
かつて、???さんも呉東と呉西という言葉を用いまして・・
「人文的な分水嶺を県内にもつというのは、他の府県にはない」
このようにお書きになっています。
1、松本清張(まつもとせいちょう)さん
2、司馬遼太郎(しばりょうたろう)さん
3、深田久弥(ふかだきゅうや) さん
ヒント・・・〇???さん
1923年(大正12年)8月 7日ー
1996年(平成 8年)2月12日
@竜馬(りょうま)がゆく
坂本竜馬さんの劇的な生涯を中心に、
同じ時代をひたむきに生きた若者達を描いています。
お分かりの方は数字もしくは???の中の人物名をよろしくお願いします。







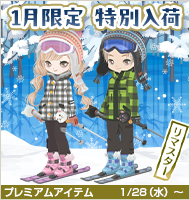












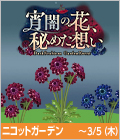






スズラン☆さん、昨夜疲労のあるなか、
こうして、コメントをありがとうございます。
そうですね、このように富山県には成立までに沢山の出来事がありますね。
はい、そうですね、色々とありますね。
現在こちらの気温は24℃と上昇をして蒸し暑いのですが、
スズラン☆さんの所はいかがでしょうか?
どうか該当の場合は、体調を崩さないように水分補給をいかがでしょうか?
色々あったんですね~
かげねこちゃん、お忙しい朝にコメントとお答えをありがとうございます。
そうですか、バッチリ調べてくださりましたか。
どうもありがとうございます。
問題の答えは2番の司馬遼太郎(しばりょうたろう)さんです。
素晴らしいですね!!完璧です!!
どうもおめでとうございました(祝)
今回はバッチリ調べましたよ。
2、司馬遼太郎(しばりょうたろう)さん
ですね。