小満
- カテゴリ:勉強
- 2025/05/21 01:01:55
こんばんは!21日(水)は西日本では雨が降り、
雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。
北陸や東北も雲が広がり、所により雷を伴った激しい雨が降る見込みです。
その他の地域は概ね晴れますが、午後はにわか雨や雷雨の所もありそうです。
【小満】 しょうまん
☆小満は二十四節気の立春から数えて8番目です。
毎年5月21日頃で2025年は5月21日小満にあたります。
期間でいいますと5月21日(水)から6月4日(水)の、
芒種(ぼうしゅ)の前日までになります。
<概要>
〇小満
@小満の意味
・小:少し
・満:みちる
このような意味がありまして、つまり「少し満ちる」という意味です。
これは自然界のあらゆる命が成長しまして、
万物が少しずつ道始める様子を表現しています。
★言葉の由来
古代中国の農業暦にあります。
二十四節気の一つとして、
作物の実りが少しずつ見え始める頃であることから、
「小満」という名が付けられました。
@二十四節気のなかでの位置づけ
春分や立夏に比べると影が薄いように感じる可能性もありますが、
夏の入口を本格的に感じる大切な時期です。
節気名 時期 特徴
立夏 5月 5日頃 夏の始まり
小満 5月20日頃 命が満ち始める
芒種 6月 5日頃 稲や麦の種蒔き
「初夏の中頃」に位置しまして、
気温も湿度も高まり、自然界が活発になってくるタイミングです。
@小満が表す季節感や自然の変化
・稲や麦が実り始める ・草花が生い茂る
・昆虫や小動物の活動が活発になる ・夜の気温も高くなってくる
これらの変化が「少しずつ満ちていく」様子を表しています。
又、梅雨の入口も近づいてきて、晴れの人雨の日が交互に現れるのも特徴です。
@昔の小満に感じていたこと
昔の人々は自然の変化を、
今よりもずっと敏感に感じ取って暮らしていました。
小満の時期になりますと、
農家は作物の育ち具合を見ながら、収穫や種蒔きの準備を整えていました。
又、山では新緑が深まりまして、草木が本格的に茂ることで、
山菜取りや薬草摘み等も盛んになったといわれています。
☆紅花
新暦の5月26日から5月30日頃は、
紅花が盛んに咲く時期という意味もあります。
原産地はエジプト等の地中海沿岸部です。
古代エジプト時代から染料として使用されてきました。
日本でも万葉集の中に「末摘花(すえつむはな)」の名前で登場しています。
■中医学では生薬
体を温め、血を補う効果がある為、
冷え性の改善や月経不順等、婦人科系のトラブルに効果的です。
ただし、出血しやすくなる為、妊婦には注意が必要です。
この頃になりますと、稲の苗が順調に育っていれば、
「今年の収穫も期待出来る」という安心感を得られる為、
「満ちる=安心」という意味でも受け取られていました。
@小満の時期・毎年同じではない理由
小満は毎年「5月20日頃~6月4日頃」までを指します。
しかし、日付は歳によって1日程度前後することがあります。
これは、二十四節気が太陽の動きをもとに決められている為です。
□具体的には
太陽黄経が60度に達した時が小満の始まりです。
その為、暦の関係で毎年微妙にズレが生じています。
■覚え方
・小満は「5月下旬」=衣替え・梅雨準備の合図
・暦上の節気なので、年によって日付が変動する
@農業との深い関わりと「万物盈満(ばんぐつえいまん)」の意味
小満は、農業と切っても切り離せない節気です。
古代中国ではこの時季「万物盈満」という言葉で表していました。
☆盈
いっぱいになるという意味がありまして、
草木や作物がどんどん満ちていく様子を表現しています。
日本でも田んぼの水入れや苗代「なわしろ」の手入れが本格化しまして、
農村は賑やかになる時期です。
畑の野菜も育ち盛りで、農家の人々は自然の恵みに感謝しつつ、
忙しい日々を送っていました。
*苗代・・・苗を育てる場所
@小満にまつわる昔ながらの風習
・田植え前の準備として「早乙女(さおとめ)達が田んぼに出る。
*早乙女・・・田植えの日に苗を植える女性
・新緑の山から薬草を摘みに行く「山菜採り」
・「お田植え祭り」等の農耕行事の準備が始まる
こうした風習は、自然と共に暮らしてきた日本人の知恵と感謝の表れです。
@衣替え
現代の衣替えは6月1日が一般的ですが、
実は小満の頃から徐々に準備するのが理にかなっています。
★初夏の陽気
小満を過ぎると昼間の気温は25℃を超えることも多く、
既に初夏の陽気です。
冬服を片付けまして、
通気性の良い服を出しておくのにはピッタリの時期です。
衣替えをすることによりまして、
冬の間にたまった湿気や黴(かび)を防ぐことが出来ます。
特に押し入れやクローゼットは、空気の入れ替えが重要です。
・着用しない冬服はしっかり洗濯してから収納
・湿気取りシートや防虫剤を一緒に入れる
・夏服を出す際はアイロンや軽い洗いでリフレッシュ
・クローゼット内を拭き掃除して埃(ほこり)や黴を除去
又、不要になった衣類はリサイクルや寄付の方法もあります。
@各地の小満に関連する地域行事
・京都:「伏見稲荷大社」さんの田植祭準備
・三重:「御田植(おたうえ)神事」の練習開始
・新潟:棚田に水を引き入れる「水入れ式」
いずれも作物への感謝と豊作祈願が込められた神事です。
@現代にも残る小満の影響
・季節限定の食材や商品(例:新茶、初ガツオ)
・自然派ライフスタイルのイベント
・気象予報士による「初夏の兆し」特集
@二十四節気と七十二候の違い
日本の季節の変化を表す暦には・・・
・二十四節気:1年を24の季節に分けたもので、小満もその一つ。
・七十二候 :二十四節気をさらに3つずつに分けた、
細かい季節の移り変わりを表す言葉。
これらがあります。
七十二候は以下の通りに分かれています。
☆初侯:蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)
桑の葉を盛んに食べて、成長する時期を表しています。
5月21日頃
★次侯:紅花栄(べにばなさかう)
紅花の花が、咲き誇る季節を表しています。
5月26日頃
☆末侯:麦秋至(むぎのときいたる)
麦の穂が熟し金色に輝く、麦の収穫期の頃を表しています。
5月31日頃
問題 小満の頃の魚介類は「食欲が無くなりがちな梅雨前」にこそ食したい、
優しい味わいが揃います。
次の中から、小満の頃の魚名を教えてください。
1、平目(ひらめ)
2、鰆 (さわら)
3、鱧 (はも)
ヒント・・・〇旬の魚名
目の横、頬から首にかけて黄金色(黄色)に染まります。
小満の頃の魚名の頬のあたりを見る機会は無いかもしれませんが、
黄金色に染まった小満の頃の魚名は脂の乗った良い状態で、
旨味もしっかり乗ってきます。
雌は卵を蓄えているので、夏の時期ならではの楽しみの一つです。
お分かりの方は数字もしくは小満の頃の魚名をよろしくお願いします。





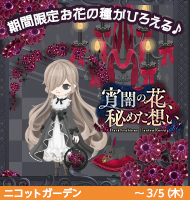














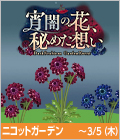






イベント開始後はとても忙しいですので、
そのようななか、コメントをありがとうございます。
そうですか、室内にも羽虫が飛び始めましたか。
なるほど~、衣替えと洗濯は済みましたか。
そうですね、少し経つと梅雨の季節ですね。
はい、そうですね、お米問題も上がっていますから、
より、稲の方が豊作になり、皆様が笑顔で過ごせることを願っています。
室内にも羽虫が飛び始めました笑。
衣替えは洗濯済みました。半纏は梅雨用に置いてます。
今年の稲は豊作でありますように(。-人-)☆
そうですか、調べてくださりましたか。
どうもありがとうございます。
そうですか、今回はチョット難しかったですか。
おおお~、これです。
はい、問題の答えはその通りで、3番の鱧(はも)が正解になります。
ああ~、なるほど、そうですね、この時期は「アジ」も旬になります。
そうでしたか、ようやく見つけてくださりましたか。
とんでもありません、間違ってたらだなんて。
かげねこちゃん、完璧ですよ!!
どうもおめでとうございました(祝)
本日はお天気が不安定な所が多く、又、蒸し暑い所もありますね。
どうか該当ならば、お身体を崩さないように、
どうか、しっかりと水分補給等をして、お過ごしくださいませ。
調べてみたのですが、今回はチョット難しかったです。
3、鱧 (はも)
これかなぁ・・・???
調べたときに出てくる魚は「アジ」が必ず出てくるのですが、ようやく見つけたのがこれでした。間違ってたら正解を教えてくださいね。