立秋
- カテゴリ:人生
- 2025/08/07 16:02:31
ニコットおみくじ(2025-08-07の運勢)

こんにちは!低気圧が通過する影響で全国的に雨が多い。
晴れる関東も含めて、局地的に激しい雷雨。
雨の地域も厳し暑さが続く。
沖縄は晴れ。
【立秋】 りっしゅう
☆立秋は二十四節気の一つで、秋の始まりを表す言葉です。
<概要>
〇立秋
@「立秋」の由来
立秋は二十四節気の中でもとくに大切な「八節」の一つです。
★八節
二十四節気の中でも特に季節の節目となる、重要な8つの節気を指します。
古来より、農作業や年中行事の目安として重視されてきました。
二十四節気は太陽の動きを基に1年を24等分した暦です。
□「立つ」「始まる」等の意味を持つ
・立春 ・立夏
・立秋 ・立冬
■季節の中間点
・春分 ・夏至
・秋分 ・冬至
これらの合計8つが「八節」と呼ばれています。
□八節の一覧
節気名 時期(目安) 意味・特徴
立春 2月 4日頃 春の始まりで、
旧暦では新年の節目。
春分 3月20日頃 昼と夜の長さがほぼ同じで、
春の中間点。
立夏 5月 5日頃 夏の始まりで、草木が繁る時期。
夏至 6月21日頃 昼が最も長くなる日。
立秋 8月 7日頃 秋の始まりで、
暦の上では秋だが暑さは続く。
秋分 9月23日頃 昼と夜の長さがほぼ同じで、
秋の中間点。
立冬 11月 7日頃 冬の始まりで、
寒さが増してくる。
冬至 12月22日頃 夜が最も長くなる日。
■八節の役割と文化的意義
◇農業の指標
作物の種蒔きや収穫のタイミングを知る為の目安です。
◆年中行事との関係
節分、彼岸、土用等の行事は、八節と密接に関係しています。
◇季節感の表現
俳句や和歌等でも、八節を用いて季節を表現しています。
@2025年の「立秋」
立秋は他の二十四節気同様にその年によって、日にちが異なります。
2025年は8月7日とされていますが、これもまた正確ではありません。
二十四節気はそもそも期間を指す言葉です。
しかし、カレンダーやニュースでは専(もっぱ)ら、
日にちの意味として使用されています。
その為、2025年の立秋は日にちであれば8月7日で、
期間であれば8月7日~22日というのが正しいです。
因みに8月23日からは、
次の二十四節気である「処暑(しょしょ)」となります。
年によって日にちが異なるのは、
閏年(うるうどし)の存在とも大きく関わります。
周知のとおり、地球の公転周期がピッタリ365日ではない為、
そのズレを調整する為に設けられたのが閏年です。
4年に1度、1年が366日となる為、
立秋等の二十四節気も同様に、およそ4年に1度、日にちが変わります。
この閏年だけを考慮して二十四節気を定めるのであれば、
毎年の日にちは分かりそうなものですが、実際には直前まで確定されません。
その理由は様々あります。
太陽が春分点を出発し、
次の年の春分点を通過する時間は、365、24日程度です。
さらに、地球の公転運動は、
地球の自転軸の変動や月の引力や他惑星の影響等によって、
毎年一定では無いことが関係しています。
その為、何十年も先の二十四節気の日にちは確定されないのです。
@「立秋」は暦上の秋の始まり
立秋は秋の始まりです。
夏の暑さが極まり、秋に向けて季節が移り変わり始める日という意味です。
つまり、暦の上では立秋が夏の暑さのピークであるとされていて、
立秋の翌日からの暑さは「残暑」と呼ばれます。
しかし、暦上では秋の始まりといっても、
実際にはまだまだ暑さの厳しい日は続きます。
どちらかといいますと、夏真っ盛りという印象を持つ人も少なくありません。
★暦上の季節と実際の季節感が異なるには理由がある
そもそも二十四節気は、昼が最も長い夏至や最も短い冬至、
そして、昼夜の時間がほぼ同一の春分と秋分等、
春夏秋冬の4つの季節に分けて、1年を24等分したものです。
□二十四節気
古代中国の、特に黄河流域の寒い気候に合わせて作られたといわれています。
当然、現代の日本とは気候が異なりますので、
季節感が異なるのは当然です。
それでも、立秋を過ぎれば日を追うごとに空や雲の様子が秋を匂わせまして、
スズムシやマツムシ等の美しい鳴き声も耳にするようになります。
@「立秋」にまつわる文化や風習
暦をご覧の通り、立秋は学生であれば夏休み真っ只中で、
立秋の期間中にはお盆もある為、立秋にまつわる行事というのは、
あまり見慣れません。
そもそも二十四節気が日本に広まったのは平安時代です。
お盆は飛鳥時代の606年に推古天皇が、
行事を行ったのが始まりだといわれています。
@「立秋」と「暑中見舞い」「残暑見舞い」
「立秋」にまつわる日本特有の文化といえるのが、
「暑中見舞い」と「残暑見舞い」です。
先にも述べたように「立秋」以降の暑さは「残暑」と呼ばれています。
その為、日頃お世話になっている方等へ送る挨拶文は、
「立秋」までは「暑中見舞い」でありまして、
翌日からは「残暑見舞い」になります。
又「立秋」の期間は8月22日、23日頃までとなりますが、
「残暑」という言葉自体は暑さが残ることを指す為、
この日までしか使用出来ないという終わりの期限は設けられていません。
残暑見舞いは8月中に送るのが一般的とされていますが、
暑さが長引く年であれば、9月に入っても「残暑見舞い」を、
送ることが出来るといわれています。
問題 「立秋」の期間に行われる行事についてですが、
次の文章等から〇に入る数字を教えてください。
一部では7月をお盆とする地域もありますが、
全国的には8月のお盆が一般的です。
全国的には8月のお盆が一般的で、
2025年も8月13日(水)~16日(土)と立秋の期間に当たります。
この頃はお墓参りやお盆祭り等ありますが、
なかでも京都の「〇山送り火」は、
毎年8月16日の立秋の期間に行われるお盆の伝統行事です。
1、一
2、三
3、五
ヒント・・・〇京都〇山送り火 〇つの送り火は全て京都市登録無形民俗文化財
毎年8月16日の夜空を彩る「京都〇山送り火」は、
お盆の精霊を迎えまして、再び浄土へ送る伝統行事です。
東山に大の字が浮かび上がり、続いて松ヶ崎に妙・法、
西賀茂に船形、大北山に左大文字、
そして、嵯峨に鳥居形が点火されます。
お分かりの方は数字もしくは〇に入る数字をよろしくお願いします。



















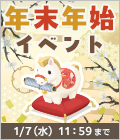











こんにちは!こちらにもコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、あくまで中国の以前の暦を参考にですからね。
七十二候の方が細かいので、そちらの方が今に近いですね。
現実は9月の半ばまで暖かい所も多いです。
標高の高い所はもう少しすると、秋めいてきますね。
問題の答えは、3番の五です。
流石ですね!どうもおめでとうございます(祝)
そうですか、初盆という期限がありますものね。
そうですか、暑い期間にですからより大変ですね。
どうか暑さと精神的なものから、体調を崩しやすいですので、
どうかゆっくり、時には休憩を入れてご従事くださいませ。
とはいえ、習慣上残暑と書いてきた経験から、
後少しの辛抱だと思うようになれます。
答え 3
初盆までに遺品整理を終わらせる為に頑張ってます。
部屋から部屋へ、荷物の移動がかなりあって大変です(^_^;)