クマエビ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/08/13 14:56:55
ニコットおみくじ(2025-08-13の運勢)

こんにちは!九州から関東甲信は日差しが戻るが、
湿った空気の影響が残り、急な雨や雷雨の所も。
北陸から北海道は概ね晴れる。
沖縄は晴れ。
【クマエビ】 熊海老 Penaeus semisulcatus De.Haan.1844
brown tiger prawn
kuruma prawn
☆クマエビは、十脚目根鰓亜目クルマエビ上科クルマエビ科、
ウシエビ属に分類されるエビの一種です。
<概要>
〇クマエビ
クマエビはクルマエビ科ウシエビ属のやや大型のエビで、
日本に限らず、生息域の各国で重要な水産資源となっています。
インドやインドネシアでは養殖も行われています。
産地によっては古くから呼ばれている名称があります。
@アシアカエビ
和歌山県をはじめ、紀伊水道から大阪湾にかけての辺りでは、
「アシアカエビ(足赤えび)」と呼ばれています。
@アカアシエビ
浜名湖周辺では「アカアシエビ(赤脚えび)」と呼ばれています。
@キジエビ
大分県辺りでは「キジエビ」等とも呼ばれています。
@高値で取引されている
クルマエビより少し大きく、味が良い上に加熱調理をしますと、
綺麗に赤く色付くこともあり、
クルマエビに次いで、高値で取引されています。
@インドにおけるエビ養殖
この産業を開発する可能性と、
問題の両方を反映する成功と挑戦の広範な歴史を持っています。
産業は1990年代初期に急速に成長し、
主に個々の農民の努力を通して出来ました。
しかし、適切な規制指針が不足している環境で運転されました。
この時間の間、エビ養殖場に携わる農場によって、
占められた全面積は劇的に増加をしましたが、
農場の85%以上は小サイズ(2ha)でした。
これらの農場において、平均海老生産はヘクタールあたり、
約0、73トンであり、他のエビ生産国と比較して低い収量を示しました。
生産性を高め、適切な規制見通しなしに、
農家は台湾やフィリピンのような国から種子ストックと飼料材料を輸入し、
より良い成長率と生産性を持つと主張しました。
この時、培養において最も頻繁に使用される種は、
Penaeusモノドンでありました。
1994年にWSSVとして知られるこのエビに影響する病気は、
インドの全産業に広がりまして、マイナスに影響しました。
そして、幾つかの利害関係者や関連産業に深刻な損失を齎(もたら)しました。
疾病管理に対する努力は研究せずに、
研究及び規制制御の必要性が主要な国家課題となっています。
1996年にインドのSupreme Countは、沿岸養殖で禁止を通過しました。
その後、インドのパリアメントの緊急セッションは、
Aquaculation Authorityを形成する為の請求を通過しました。
しかし、連続故障の為、
同時に農家は文化の為の代替候補種を探すことを始めました。
2003年のインドにおけるこの産業の主要なシフトは、
水産養殖の為の候補種として、Litopenaeus vannameiの導入で起きました。
2017年末までに文化下の面積は50%増加し、生産がほぼ83%増加し、
インドが世界で2番目に高いエビ生産者になりました。
それにも関わらず、これらの生産統計に関する疑問と、
非規制及び、又は非登録農業が実践されている程度が残りました。
2005年には沿岸水域における水産養殖と結び付いた活動を調節する為に、
沿岸養殖金利権法制定が制定されました。
この差bb業の今後の展開と可能性を考えますと、
輸出可能性を最大化するだけではなく、インドにおけるエビ養殖を保護し、
改善する為の継続規制の必要性は明らかです。
@気候変動に配慮したエビ養殖がインドネシアで成功
インドネシアの中央スラウェシ州ドンガラ県ラロンビ村で、
気候スマートエビ養殖(CSS)の手法を用いた初めての収穫が行われ、
3日間で50トン以上のエビが収穫されました。
この成果は、テクノロジーと環境保全を統合した、
持続可能なエビ養殖モデルの実現に向けた重要な一歩とされています。
★CSS手法
マングローブ林の再生とエビ養殖の生産性を向上させることを目指していて、
環境への負荷を軽減しながら、地域社会の経済発展にも寄与しています。
又、マングローブ林が持つ、炭素吸収能力の重要性も強調されまして、
持続可能な水産物の確保が期待されています。
☆マングローブの重要性
持続可能な水産物食糧安全保障を支える上で欠かせない要素です。
ラロンビ地域のエビ養殖場周辺では、
再生されたマングローブ林が年間1ha辺り、
最大7、4トンの炭素を吸収すると推定されています。
さらに、1ha辺りから500トンから1083トンの、
炭素貯蔵が見込まれることから、3、5haのマングローブ林では、
約3700トンの炭素を貯蔵する可能性があります。
マングローブ生態系は生物多様性においてもっ重要な役割を果たしていて、
マングローブガニや様々な魚類の産卵や繁殖の場となっています。
@生態
大西洋の西部や南部からインド洋、紅海の沿岸各地に広く分布しまして、
日本海側では富山湾辺りから西太平洋側では、
千葉県辺りより南の沿岸に分布しています。
★海外
・韓国 ・台湾
・中国 ・フィリピン
・インドネシア ・オーストラリア東岸
・タイ ・マレーシア
・インド ・パキスタン
・ミャンマー ・モーリシャス
・エジプト ・イスラエル
・レバノン沿岸
これらの地域に分布しています
☆生息
水深70m程度までの砂泥や泥底に生息しますが、
多くは水深20m以浅にみられます。
★産卵期
6月下旬から8月中旬頃の夏で、
5月下旬に和歌山県雑賀崎(さいがざき)港に水揚げされたものは、
多くが卵巣が発達した状態です。
@特徴
大きさは体長13cm程のものが多いですが、
雌の方が少し大きくなる傾向がありまして、
大きいものだと、体長23cm、100gを超えます。
☆体の形
クルマエビと似た細長い円筒形で、
赤褐色の地色に淡く色の薄い縞模様があります。
頭胸甲の額角左右に正中溝がありますが、溝は浅く前半部で消失します。
尾節に側棘はありません。
★別名の由来
他のエビと違う大きな特徴は赤い触覚に白い縞模様があることと、
歩脚や腹脚が赤色に白く丸い斑があり、綺麗な紅白に見えることで、
アシアカエビやアカアシエビという別名の由来になっています。
☆額角
上縁に6~8歯、下縁にも2~4歯(3歯が多い)ありまして、
クルマエビに比べて、殻は柔らかいです。
問題 クマエビの産地についてですが、
次の文章の〇〇に入る県名を教えてください。
クマエビは流通量は少なく、活け物の主な産地は、
和歌山県や浜名湖のある〇〇県、熊本県や大分県等です。
1、静岡
2、滋賀
3、島根
ヒント・・・〇浜名湖
浜松市と湖西(こさい)市に跨る湖で、汽水湖です。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る県名をよろしくお願いします。





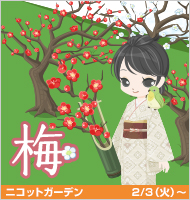




















こんにちは!お忙しいところ、こちらにもコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですね、美味しそうですね。
なるほど~、印象はなかなか拭い去りにくいですものね。
問題の答えは、1番の静岡県です。
浜名湖は海の魚のスズキや湖で摂れるシジミも生息していたりと、
日本の中でも色々な生物がおられますよね。
勿論、うなぎも盛んですね。
浜松という所は自動車の免許を取得する為に教習所合宿に通ったり、
そして、親友が生まれた場所で、数多く行った所です。
結構面白い街ですので、おすすめです。
スズランさん、機会がありましたらいかがでしょうか?
勿論、うなぎも美味しかったです。
インドの生産物は、衛生管理がずさんな印象があって、
買うのは避けたいです。
答え 1