鉄道の日
- カテゴリ:レジャー/旅行
- 2025/10/14 00:44:52
こんばんは!14日(火)は、九州から東北南部にかけては日本海側から雨が降り、
次第に雨の降る範囲が太平洋側に広がるでしょう。
激しい雷雨となる所もありそうです。
東北北部から北海道は概ね晴れますが、夜には道北で雨の降る所があるでしょう。
南西諸島は晴れたり曇ったりとなり、所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。
尚、台風23号は今後、日本の東寄りに進む見通しです。
【ハロウィンコーデ/コーデ付き日記投稿イベント】
A、ハロウィンニャイト ねこみみパーカー(M)です。
【鉄道の日】 てつどうのひ Railway Day
Railroad Day
☆鉄道の日は日本で最初の鉄道が開通したことを記念して、
毎年10月14日に行われる行事です。
<概要>
〇鉄道の日
日本には数多くの記念日がありますが、
その中でも鉄道ファンや旅好きの人々にとって特別な日が「鉄道の日」です。
毎年10月14日に制定されているこの記念日は、
鉄道の歴史や役割を振り返り、未来の鉄道を考えるきっかけとなっています。
@鉄道の日の由来、新橋駅から横浜駅間の開業
鉄道の日のルーツは、
1872年(明治5年)10月14日に遡(さかのぼ)ります。
この日、日本初の鉄道が、
「新橋駅(現:汐留付近)」と「横浜駅(現:桜木町駅)」の間に開業しました。
全長29kmという短い路線でしたが、
日本の近代化の象徴として、非常に大きな意味を持っていました。
当時の鉄道はイギリスの技術者や機関車に依存していまして、
日本が近代国家として発展する為の第一歩でした。
西洋化が進む明治時代において、
鉄道は単なる交通手段ではなく、国力の象徴でもありました。
@「鉄道記念日」から「鉄道の日」へ
鉄道を記念する日自体は戦前から存在していました。
★鉄道記念日
1922年(大正11年)、
鉄道開業50周年を記念して「鉄道記念日」が制定されまして、
その後、長らく10月14日は鉄道を祝う人されてきました。
□日本の鉄道の夜明け
1872年(明治5年)10月14日、
日本で初めての鉄道が新橋と横浜間に開業しました。
江戸時代が終わったばかりで、
ペリー来航から20年も経っていませんでした。
そして、明治5年といえば明治維新の真っ只中です。
まさに日本の鉄道は、日本の夜明けとともに始まりました。
■イギリスで本格的に始まる
イギリスでは1825年に世界初の蒸気機関車による、
鉄道が開業していました。
この鉄道は石炭輸送が目的でした。
産業革命によって工業化が目覚ましかった当時のイギリスでは、
石炭が大量に消費されるようになっていました。
石炭は発明された蒸気機関の燃料として必要だったからです。
重くてかさばる石炭の効率的な輸送方法として鉄道が開発されました。
さらに1830年には、イギリスのマンチェスターとリバプール間で、
旅客運転も始まりました。
その後、これらの鉄道事業の成果によりまして、
1820年代から1830年代にかけて、
アメリカやドイツ、フランス、ロシア等の欧米にも広がっていきました。
1863年には早くもロンドンで世界初の地下鉄が開業しています。
日本初の地下鉄開業は、1927年(昭和2年)です。
□日本と鉄道との出会い
1840年代の江戸幕府がオランダから入手した、
「オランダ風説書」とは別の「別段風説書」に、
鉄道に関する情報が含まれていました。
つまり、江戸時代には既に鉄道の存在を認識していました。
◆別段風説書
アヘン戦争以降、幕府はオランダ風説書とは別に、
海外に関する、より詳細な情報を得る必要が生じたので、
提出してもらっていました。
当時の海外の貴重な最新情報について知ることが出来ました。
この頃、土佐(現:高知県)のジョン万次郎(中浜万次郎)さんは、
1841年に漁で遭難して、無人島に流れ着きました。
その後、アメリカの捕鯨船に救助されて渡米します。
帰国後、滞在中に鉄道に乗車したことを証言しています。
ジョン万次郎さんは、
初めて鉄道に乗車した日本人と考えられています。
1853年(嘉永6年)にペリーさんが黒船で来航します。
1854年に再び来航した時、
江戸幕府に蒸気機関車の模型が献上されました。
模型でしたが初めて鉄道を目にしたのです。
この模型は、江戸城でも走らせています。
開国によって外国との関係が始まりますと、
欧米各国は日本での鉄道計画を考えるようになります。
これにより、江戸幕府への売り込みを図る国も出てきます。
政権が江戸幕府から明治新政府にバトンタッチされますと、
新政府は外国に建設や経営を委ねるのではなく、
自国で鉄道を敷設する方針を取ります。
殖産興業を推し進める為には、
国策として鉄道の建設は不可欠であると考えました。
■開業までの経緯
1869年(明治2年)に政府によりまして、
中仙道経由で東京と京都間を幹線とする鉄道の敷設が決定されますが、
まずは大都市と近郊を結ぶということで、
その支線として、東京と横浜間の開通を最優先させることになりました。
鉄道事業の中心にあたったのが井上勝さんでした。
井上勝さんは1863年(文久3年)からロンドンに渡航しまして、
鉄道に関する知識や技術を学んできます。
帰国後、責任者となって陣頭指揮にあたります。
1870年(明治3年)、
イギリス人のエドモンド・モレルさんという技術者を呼びまして、
測量から開始されます。
レール軌間、つまりゲージに関しては、
1067mmの狭軌(きょうき)を採用しました。
これは、当時国際的に普及していた、
1435mmの標準軌より狭い軌間です。
問題 日本の鉄道のレール軌間(ゲージ)についてですが、
1067mmの狭軌を採用したのか、
それとも、1435mmの標準軌を採用したのか、
又は、別のレール軌間を採用したかについて、教えてください。
1、狭軌
2、標準軌
3、別の狭軌
ヒント・・・〇正解のレール軌間(ゲージ)
そこで狭軌か標準軌にするかで検討されました。
これについて当時、
明治政府によって雇われていたモレルさんの進言もありまして、
正解のレール軌間(ゲージ)を採用しました。
正解のレール軌間(ゲージ)の方が、
コストがかかりにくいことや、
山間部が多い日本の地形で真っ直ぐに敷きづらいことから、
線路幅が狭い方が良いのではないかということが理由です。
@エドモンド・モレル さん
イギリス人でオーストラリアやニュージーランドで、
土木技術者として活動されました。
さらに北ボルネオ(現・マレーシア・サバ州とラブアン)で、
鉄道建設に携わります。
日本へは1870年に来日されました。
お分かりの方は数字もしくは日本の鉄道のレール軌間(ゲージ)についてですが、
どのレール軌間(ゲージ)を採用したかをよろしくお願いします。





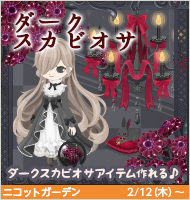

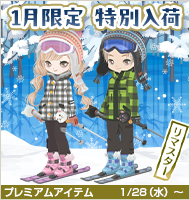












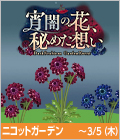





そうですね、案外思ったよりも経っていませんね。
そうですね、確かに奴隷扱いされた国もありますものね。
おっしゃる通り、そうならなかったことで、日本のたゆまぬ努力に感謝ですね。
問題の答えですが、1番の狭軌ですね。
やっぱり日本の土地は狭いので、広い線路だと厳しいですね。
しかし、広い線路でやっていたらもっと安定出来ましたし、スピードを出しやすいですね。
色々とこうしたことも考えられたことも考えられたはずで、狭軌が正しいのでしょうね。
スズラン☆さん、勿論正解です。
どうもおめでとうございました(祝)
近代文明を目指すことで、後の戦争で奴隷扱いされることなく済んだと思うので、
日本のたゆまぬ努力に敬意を表します。
答え 1