トゲザコエビ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/10/25 16:50:07
ニコットおみくじ(2025-10-25の運勢)

こんにちは!九州から関東は昼頃から雨で、近畿、東海では夜に激しく降る所も。
北陸から北海道は晴れ間も出るが、午後は所々で雨。
沖縄は晴れ。
【トゲザコエビ】 棘雑魚蝦 Argis toyamaensis(Yokoya,1933)
Mosa shrimp
☆トゲザコエビは、エビジャコ科クロザコエビ属の日本の深海に生息する、
甲殻類の一種です。
<概要>
○トゲザコエビ
トゲザコエビはエビジャコ科の一種で、
この名前よりも「ガスエビ」や「ドロエビ」、「モサエビ」等の、
地方名の方が馴染みがあることも多いようです。
日本海沿岸の産地で食されてきた、とても美味しいエビで、
「見た目は悪いが、甘くて美味しいエビ」として知られています。
これとよく似たものに「クロザコエビ」というのもいます。
トゲザコエビより少し白っぽいくらいで、
ほとんど同じ姿をしていて、一緒に混ざって販売されていることもあります。
「食材魚介大百科」や「旬の食材-冬の食材」等の書籍により、
本種をトゲクロザコエビ(Argis dentata(Rathbun,1902)と、
紹介しているものもあり、
和名トゲクロザコエビとされる種(Argis ochotensis Komai,1997)と、
紛らわしい種もあります。
近年、日本近海に分布するトゲザコエビが、
Argis ochotensis Komai,1997)とは、
別種として扱われるようになりました。
こうした深海エビ類の分類に関しては、
まだはっきりとしていないことが多いようです。
@トゲザコエビとクロザコエビの違い
トゲザコエビは「黒っぽくスマート」で、
クロザコエビは「ベージュでずんぐり」とした、
見た目や生息域、味に違いがあります。
★見た目の違い
特徴 トゲザコエビ クロザコエビ
体色 暗色(黒っぽい) 薄いベージュ
体型 スマート ずんぐり
殻の硬さ やや硬い 柔らかい
模様 体節の殻の下半分に白い縁取り 尾に近い節に、
鞍掛状の暗色横帯
体長 約12cm 約13cm以上
☆生息域の違い
■トゲザコエビ
より深い海域(水深1000m以上)にも生息していて、深海性が強いです。
□クロザコエビ
水深300mより浅い海域に生息していて、
日本海沿岸(島根~北海道)に分布しています。
★呼び名と味の違い
□地方名
◆トゲザコエビ
・モサエビ、クロエビ、ガスエビ
◇クロザコエビ
・ホンモサ、シロエビ、シロガスエビ
■味の傾向
・両者とも甘エビ以上の甘味と旨味があるとされていて、
刺身や握りで人気があります。
・クロザコエビの方が、濃厚でコクがあるという声もあります。
□見分け方のコツ
・並べて比較すると違いが分かりやすいですが、単体では判別が難しいです。
・模様や体型、色合いに注目しますと識別しやすいです。
どちらも「幻のエビ」と呼ばれる程、希少で美味です。
市場では区別をされずに同じ名前で扱われることも多いですが、
味や見た目に拘(こだわ)るなら、是非違いを覚えておくと楽しみが増します。
@生態
トゲザコエビは、日本海の水深200~1000mという、
深い海の泥底に生息しています。
近縁種のクロザコエビとは、水深250m辺りを境に、
その生息域が分かれるとみられています。
★分布
分布に関してはまだ未解明のようで、
山陰以北から日本海からオホーツク海とみられています。
☆産卵期
1~3月とされていますが、
初夏にも抱卵したものが多く、抱卵期間が長いです。
又、隔年でしか産卵しないとみられています。
@特徴
★体長
トゲザコエビは体長12~13cm程の大きさで、
近縁種のクロザコエビより少し大きいです。
☆外見
全体的にガサガサした姿で、
額角(がっかく)は棘程度しかなく、両目が並んで突き出ています。
■額角 rostrum
甲殻類の頭胸甲の前端中央から突き出した角状の突起で、
エビ類で特によく見られる構造です。
◇基本情報
▲位置
頭胸甲(背甲)の前端中央から前方に突き出しています。
△形状
剣上又は棘状で、上下の縁に鋸歯状の棘が並ぶことが多いです。
▲構造
通常は背甲と一体化していて、動かない不動構造体です。
△例外
シャコ類やコノハエビ類では関節構造になっていまして、
蝶番のように可動する「額板(rostral plate)と呼ばれています。
◆額角の役割と分類上の意義
△分類の手がかり
額角の形状や棘の数や配置は、
エビ類の分類や種の識別に重要な特徴です。
▲幼生期の特徴
十脚類のゾエア幼生では、額角が長い棘状に発達し、
額棘「がっきょく(rostral spine)」と呼ばれています。
△他の節足動物にも存在
アミ類、端脚類、カイアシ類、昆虫類、
ミジンコ類等にも類似構造が見られます。
◆額角の英語「rostrum」の広い意味
「rostrum」は甲殻類の額角だけではなく、
哺乳類の鼻口部、鳥類の嘴(くちばし)、蜘蛛(くも)の上唇、
イモガイの吻鞘(ふんしょう)等、
様々な突起構造を指す語として使用されます。
△吻鞘
動物の口先やその周辺の構造物を指す用語です。
額角はエビ類の見た目だけではなく、分類学的にも非常に重要な構造です。
トゲザコエビやクロザコエビの識別にも、
額角の形状が手がかりになることがあります。
☆体色
全体に赤褐色のものが多いですが、
獲れた場所によって、クロザコエビのような黄褐色のものもいます。
しかし、クロザコエビに見られる腹節の背部に褐色の帯が本種には無く、
頭胸甲の側面に白い斑紋があり、
腹節の腹側が同じ白色で縁取られています。
★棘
尾の付け根に付いている左右1対の棘が、
トゲザコエビが鋭く長く尖っているのに対し、
クロザコエビは丸いことでも判別出来ます。
問題 トゲザコエビの漁獲場所についてですが、
次の文章の〇○に入る都道府県名を教えてください。
○男鹿(おが)半島沖
○○県西部に位置する男鹿半島の沖合は、
深海性の魚介類が豊富な漁場です。
トゲザコエビは、水深200~1000mの泥底に生息していまして、
底曳き網漁で漁獲されます。
1、秋田
2、宮城
3、島根
ヒント・・・○火山地形
寒風山や男鹿三山等、火山活動によって形成された地形が多く、
目潟火山群(マール)も存在します。
@寒風山(かんぷうざん)
○○県男鹿市にある、条鋼約355mの小規模な火山です。
@男鹿三山(○○県男鹿市)
真山(565m)、本山(715m)、毛無山(617m)です。
お分かりの方は数字もしくは○○に入る都道府県名をよろしくお願いします。





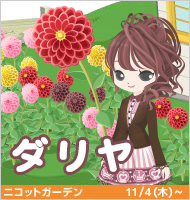











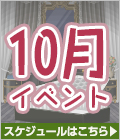










こんばんは!お忙しい日曜日の夕方にコメントとお答えをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですか、凄いですね!見たことがありますか。
おおお~、さらにお刺身で食べたことがある可能性ですか。
地域によっては、珍しい食材がポピュラーであったりしますものね。
はい、なかなかどちらがどちらかまでは分かりにくい生物ですね。
問題の答えですが、1番の秋田が正解ですね。
男鹿半島(男鹿市)は「なまはげ」で有名な所で、
頭の中に「なまはげ」=秋田になっていると、分かりやすい問題ですね。
スズラン☆さん、流石ですね!完璧です!
こうしたエビ類も豊富な秋田県、素晴らしい自然がある為ですね。
見たことはあるけれど、名前も知らずにお刺身で食べたことがあるかも?
どちらかは当然わからないです(笑)
答え 1